夏休み [misc]
いつもご訪問いただき、ありがとうございます。本日から8月末(予定)まで夏休みをとることにしました。しばらく更新はお休みします。再開時には、またご贔屓下さい。
先日、ボスが大絶賛&強力推薦する「ヨブへの答え」(C.G.ユング著、林道義訳;みすず書房)を読んでみました。旧約聖書の「ヨブ記」を題材に、ユングが精神分析的アプローチにより神(ヤーウェ)の真の姿をあぶり出す痛快な本でした。ヨブ記というのは、ヨブという信心深い義人に対し、神が信仰心を試すという名目で「私は神だ!どうだまいったか」と執拗に暴虐の限りを尽くすお話です。ユングによると、ヨブ記成立前後における神(正確には、人々の持つ神という集合的イメージ)は、自分勝手で幼くて傍若無人で悪魔の囁きに簡単に乗せられる、軽率で克己心のかけらも感じられない存在だったようです。ユングが精魂込めて紡ぎ出した大変まじめな本なのですが遠慮会釈ない表現の数々に、読みながら吹き出してしまいました。そして、「子供たちを責めないで」(秋元康作詞)という昔ちょっとはやった歌の一節を思い出しました。「子供は幼稚で 礼儀知らずで 気分屋で 前向きな姿勢と 無いものねだり 心変わりと 出来心で生きている 甘やかすとつけあがり 放ったらかすと悪のりする」という部分です。ヨブをいじめた神とそっくりです。私はスペイン系カトリック幼稚園およびドイツ系カトリック中学・高校に通いキリスト教教育を受けましたが、キリスト教に親しみを持つには至りませんでした。しかし、神という概念や聖書がこんなにおもしろいものだということを見直し「ヨブへの答え」を楽しく読めるのは、過去に受けた教えのおかげです。キリスト教とか神について関心がない方でも、人間の精神や心理に興味があれば、この本は刺激的だと思います。
天気予報によると残暑は厳しくなりそうです。皆さま、くれぐれもご自愛ください。ごきげんよう。ご武運をお祈りします。
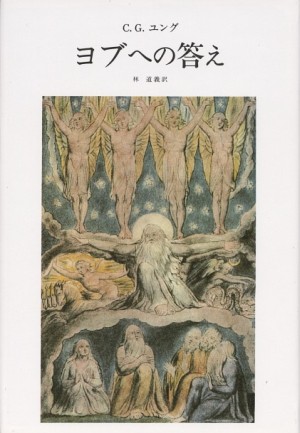
先日、ボスが大絶賛&強力推薦する「ヨブへの答え」(C.G.ユング著、林道義訳;みすず書房)を読んでみました。旧約聖書の「ヨブ記」を題材に、ユングが精神分析的アプローチにより神(ヤーウェ)の真の姿をあぶり出す痛快な本でした。ヨブ記というのは、ヨブという信心深い義人に対し、神が信仰心を試すという名目で「私は神だ!どうだまいったか」と執拗に暴虐の限りを尽くすお話です。ユングによると、ヨブ記成立前後における神(正確には、人々の持つ神という集合的イメージ)は、自分勝手で幼くて傍若無人で悪魔の囁きに簡単に乗せられる、軽率で克己心のかけらも感じられない存在だったようです。ユングが精魂込めて紡ぎ出した大変まじめな本なのですが遠慮会釈ない表現の数々に、読みながら吹き出してしまいました。そして、「子供たちを責めないで」(秋元康作詞)という昔ちょっとはやった歌の一節を思い出しました。「子供は幼稚で 礼儀知らずで 気分屋で 前向きな姿勢と 無いものねだり 心変わりと 出来心で生きている 甘やかすとつけあがり 放ったらかすと悪のりする」という部分です。ヨブをいじめた神とそっくりです。私はスペイン系カトリック幼稚園およびドイツ系カトリック中学・高校に通いキリスト教教育を受けましたが、キリスト教に親しみを持つには至りませんでした。しかし、神という概念や聖書がこんなにおもしろいものだということを見直し「ヨブへの答え」を楽しく読めるのは、過去に受けた教えのおかげです。キリスト教とか神について関心がない方でも、人間の精神や心理に興味があれば、この本は刺激的だと思います。
天気予報によると残暑は厳しくなりそうです。皆さま、くれぐれもご自愛ください。ごきげんよう。ご武運をお祈りします。
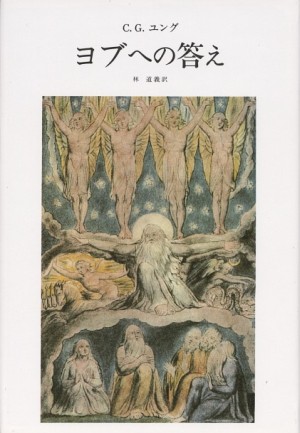
2011-07-29 11:11
コメント(0)
緑膿菌肺炎~投与期間 [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part II: Antimicrobial Resistance, Pharmacodynamic Concepts, and Antibiotic Therapy
CHEST 2011年5月号より
抗菌薬投与期間
抗菌薬の至適投与期間を明らかにするため、VAPを発症したICU患者51名についての前向き無作為化二重盲検試験が行われ、投与期間8日と15日のどちらが優れているが検討された。対象患者中42名において、気管内採痰の定量培養で緑膿菌に感染していることが確認された。抗菌薬投与期間が8日であった群の方が15日群よりも再発率が有意に高かった(40.6% vs 25.4%)。ただし、ICU滞在期間や死亡率は同等だった。他方、多剤耐性緑膿菌の出現率は15日群の方が有意に高かった。これは、往々にして見過ごされている重大な注意点である。投与期間を決定する際は、再発の危険性と、多剤耐性もしくは汎薬剤耐性緑膿菌の発生リスクとを症例ごとに比較考量する必要がある。したがって、緑膿菌肺炎の診断が確定されておらず、抗菌薬投与開始から3日以内に状態が安定すれば、投与期間は8日にすべきである。一方、抗菌薬の予測的投与が緑膿菌肺炎に対して奏功しなかったり、それまでのICUにおける経過が複雑であったりする症例では、投与期間を15日にする方がよいかもしれない(Fig. 2)。
ICUにおける緑膿菌肺炎に対する抗菌薬吸入用製剤:嚢胞性線維症や肺移植患者の肺炎に対するアミノグリコシド系薬またはコリスチンの吸入製剤の有効性が検討されている。アミノグリコシド系薬の吸入剤を用いると、高い肺組織アミノグリコシド濃度を達成することができる一方で、血中濃度は無視できる程度の低いレベルに止まる。
症例報告や遡及的症例対照研究において、コリスチンの吸入製剤(多くが静注製剤との併用)が肺炎に対して有効であると報告されている。VAP患者100名にコリスチン吸入製剤を投与した前向き無作為化試験では、転帰が良好であった患者の割合は生食を吸入させた対照群と同等であった(約50%)。吸入製剤の併用療法としては、コリスチンとトブラマイシンの吸入製剤を併用する方法が、嚢胞性線維症患者の多剤耐性緑膿菌肺炎難治例に実施されている。嚢胞性線維症患者の緑膿菌感染に対するアズトレオナムの吸入製剤の適応が認可されている。
まとめ
多剤耐性緑膿菌は複数の耐性機構を備えているため、ICU領域における深刻な問題として耳目が集まっている。動物実験、in vitro研究、PK/PDデータおよび幅広い臨床研究で得られた知見を総合し、我々は抗緑膿菌βラクタム系抗菌薬と、アミノグリコシド系薬または抗緑膿菌キノロン系薬を併用する抗菌療法を推奨する。この際、キノロン耐性緑膿菌が増加しているため、キノロン系薬の使用は控えるべきであるかもしれない。可能であればβラクタム系薬は持続静注によって投与すべきである。なぜなら、βラクタム系薬は持続静注すると、抗菌活性がより強く、より長く発揮されるとともに、人件費の削減にもつながるからである(看護師や薬剤師が費やす時間の削減)。アミノグリコシド系薬は薬力学的にも利便性の上でも一日一回投与が優れている。アミノグリコシド系薬の投与期間は、可能な限り5日未満とする。多剤耐性緑膿菌に対して抗菌活性のある抗菌薬がポリミキシン(コリスチン)をおいて他にないことがよくあるため、一部のICUではポリミキシンが使用されている。本レビューでは、ICU患者の肺炎に対する抗菌薬の予測的投与についての実践的アルゴリズムを示した。
教訓 緑膿菌肺炎の診断が確定されておらず、抗菌薬投与開始から3日以内に状態が安定すれば、投与期間は8日にします。一方、抗菌薬の予測的投与が緑膿菌肺炎に対して奏功しなかったり、それまでのICUにおける経過が複雑であったりする症例では、投与期間を15日にする方がよいかもしれません。ただし、投与期間が長引くと多剤耐性緑膿菌が出現しやすくなるので注意が必要です。
CHEST 2011年5月号より
抗菌薬投与期間
抗菌薬の至適投与期間を明らかにするため、VAPを発症したICU患者51名についての前向き無作為化二重盲検試験が行われ、投与期間8日と15日のどちらが優れているが検討された。対象患者中42名において、気管内採痰の定量培養で緑膿菌に感染していることが確認された。抗菌薬投与期間が8日であった群の方が15日群よりも再発率が有意に高かった(40.6% vs 25.4%)。ただし、ICU滞在期間や死亡率は同等だった。他方、多剤耐性緑膿菌の出現率は15日群の方が有意に高かった。これは、往々にして見過ごされている重大な注意点である。投与期間を決定する際は、再発の危険性と、多剤耐性もしくは汎薬剤耐性緑膿菌の発生リスクとを症例ごとに比較考量する必要がある。したがって、緑膿菌肺炎の診断が確定されておらず、抗菌薬投与開始から3日以内に状態が安定すれば、投与期間は8日にすべきである。一方、抗菌薬の予測的投与が緑膿菌肺炎に対して奏功しなかったり、それまでのICUにおける経過が複雑であったりする症例では、投与期間を15日にする方がよいかもしれない(Fig. 2)。
ICUにおける緑膿菌肺炎に対する抗菌薬吸入用製剤:嚢胞性線維症や肺移植患者の肺炎に対するアミノグリコシド系薬またはコリスチンの吸入製剤の有効性が検討されている。アミノグリコシド系薬の吸入剤を用いると、高い肺組織アミノグリコシド濃度を達成することができる一方で、血中濃度は無視できる程度の低いレベルに止まる。
症例報告や遡及的症例対照研究において、コリスチンの吸入製剤(多くが静注製剤との併用)が肺炎に対して有効であると報告されている。VAP患者100名にコリスチン吸入製剤を投与した前向き無作為化試験では、転帰が良好であった患者の割合は生食を吸入させた対照群と同等であった(約50%)。吸入製剤の併用療法としては、コリスチンとトブラマイシンの吸入製剤を併用する方法が、嚢胞性線維症患者の多剤耐性緑膿菌肺炎難治例に実施されている。嚢胞性線維症患者の緑膿菌感染に対するアズトレオナムの吸入製剤の適応が認可されている。
まとめ
多剤耐性緑膿菌は複数の耐性機構を備えているため、ICU領域における深刻な問題として耳目が集まっている。動物実験、in vitro研究、PK/PDデータおよび幅広い臨床研究で得られた知見を総合し、我々は抗緑膿菌βラクタム系抗菌薬と、アミノグリコシド系薬または抗緑膿菌キノロン系薬を併用する抗菌療法を推奨する。この際、キノロン耐性緑膿菌が増加しているため、キノロン系薬の使用は控えるべきであるかもしれない。可能であればβラクタム系薬は持続静注によって投与すべきである。なぜなら、βラクタム系薬は持続静注すると、抗菌活性がより強く、より長く発揮されるとともに、人件費の削減にもつながるからである(看護師や薬剤師が費やす時間の削減)。アミノグリコシド系薬は薬力学的にも利便性の上でも一日一回投与が優れている。アミノグリコシド系薬の投与期間は、可能な限り5日未満とする。多剤耐性緑膿菌に対して抗菌活性のある抗菌薬がポリミキシン(コリスチン)をおいて他にないことがよくあるため、一部のICUではポリミキシンが使用されている。本レビューでは、ICU患者の肺炎に対する抗菌薬の予測的投与についての実践的アルゴリズムを示した。
教訓 緑膿菌肺炎の診断が確定されておらず、抗菌薬投与開始から3日以内に状態が安定すれば、投与期間は8日にします。一方、抗菌薬の予測的投与が緑膿菌肺炎に対して奏功しなかったり、それまでのICUにおける経過が複雑であったりする症例では、投与期間を15日にする方がよいかもしれません。ただし、投与期間が長引くと多剤耐性緑膿菌が出現しやすくなるので注意が必要です。
2011-07-28 07:15
コメント(0)
緑膿菌肺炎~治療アルゴリズム [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part II: Antimicrobial Resistance, Pharmacodynamic Concepts, and Antibiotic Therapy
CHEST 2011年5月号より
ICUにおける肺炎治療アルゴリズム
ICUにおける緑膿菌肺炎の治療方針を、読者に分かりやすいよう図にまとめた(Figs 1, 2)。この治療方針の一部は、SinghらおよびTorresが提案している方法を踏襲して作成された。肺に浸潤影がありICU肺炎として治療が行われている患者の実に50%~70%は、実は感染ではなくて、ARDS、鬱血性心不全、無気肺などの感染以外の病態のため浸潤影を呈しているという点を強調したい。したがって、患者が本当に呼吸器系の感染症であると確証を得ることが重要である。感染していないICU患者や、重症ではないICU患者に見境なく抗菌薬を投与すると死亡率が上昇することが分かっているからである。重症度の評価は必須である(Fig. 1)。点数化して評価するのに便利なものとして、APACHEスコアやPitt Bacteremiaスコアがある。重症例であれば、抗菌薬を予測的に投与する必要がある。多剤耐性緑膿菌定着または感染の既往があったり、その時点までのICU滞在期間中にすでに抗菌薬を投与されていたりすると、多剤耐性菌がいつ発生してもおかしくない。一般的には、カルバペネム系薬以外の抗緑膿菌βラクタム系薬が選択されることが多い(Fig. 1, Table 1)。自施設における感受性パターンに基づいて、はじめの予測的投与に用いる抗菌薬を選択しなければならない。過去30日以内にすでに抗緑膿菌βラクタム系薬が投与されている場合は、別の系統の抗緑膿菌抗菌薬を選択する。アミノグリコシド系薬を従とする多剤併用を行う場合は、細菌検査で効果が確認されるか、臨床的に改善が認められれば、アミノグリコシド系薬は3~5日以内に中止するとよいだろう。
CPISスコアは、短期間の単剤投与が適している症例を判別するためのスクリーニングに利用される(Fig. 1)。すでに述べた通り、状態が安定している患者では緑膿菌が分離されても感染ではなくて定着であるに過ぎないことが往々にしてある。CPISスコアを用いれば、悪気はないが無知な関係者が本来必要のない抗緑膿菌薬を投与してしまうのを防ぐことができる。治療開始から丸3日が経過したら、臨床的評価を再度実施すべきである(Fig. 2)。その際には痰培の結果が必要である(Fig. 2)。当初の状態が中等症以下で単剤投与が行われていた症例では、3日間の単剤投与後もCPISが依然として低ければ抗菌薬を中止してもよい。その後は、感染の徴候が出現しないかどうかを注意深く観察する。
コリスチンの投与
多剤耐性緑膿菌の出現をうけ、コリスチンに再び脚光が当たっている(Fig. 2)。ICU肺炎を対象とした対照群のない数編の研究で、コリスチンが有効であるとの結果が得られている。多剤耐性緑膿菌または多剤耐性アシネトバクターによるVAPについての症例対照研究が行われ、イミペネム投与例では72%、コリスチン投与例では75%において臨床的に有効性が認められた。前述の通り、PK/PDに関する研究ではコリスチンは6~8時間おきの投与の方が、12時間おきよりも好ましいことが分かっている。
動物実験およびin vitro研究において、コリスチンとリファンピシン、コリスチンおよびカルバペネムの組み合わせは緑膿菌に対して相乗効果を発揮することが示されている。しかし、ヒトを対象とした研究ではコリスチンを含む多剤併用の有効性を裏付ける結果は得られていない。コリスチンはもとより市販されているあらゆる抗菌薬にin vitroで耐性を示す汎薬剤耐性緑膿菌(PDRP)によるVAP症例も発生している。その主な危険因子はコリスチンとカルバペネムの多剤併用が13日を超えて実施した場合であると報告されている。
コリスチンは可逆性の腎毒性と可逆性の神経毒性を発現することが知られている。しかし、重症患者では色々な異常が入り組んで存在しているため、このような有害作用を薬剤によるものなのかそうでないのかを見極めるのは困難である。コリスチンによる腎毒性は、解決可能な問題である。コリスチンは、腎毒性はあるのに聴神経毒性はない珍しい薬剤である。
教訓 肺に浸潤影がありICU肺炎として治療が行われている患者の50%~70%は、感染以外の原因によって浸潤影を呈しています。感染していないICU患者や、重症ではないICU患者に見境なく抗菌薬を投与すると死亡率が上昇することが分かっています。
CHEST 2011年5月号より
ICUにおける肺炎治療アルゴリズム
ICUにおける緑膿菌肺炎の治療方針を、読者に分かりやすいよう図にまとめた(Figs 1, 2)。この治療方針の一部は、SinghらおよびTorresが提案している方法を踏襲して作成された。肺に浸潤影がありICU肺炎として治療が行われている患者の実に50%~70%は、実は感染ではなくて、ARDS、鬱血性心不全、無気肺などの感染以外の病態のため浸潤影を呈しているという点を強調したい。したがって、患者が本当に呼吸器系の感染症であると確証を得ることが重要である。感染していないICU患者や、重症ではないICU患者に見境なく抗菌薬を投与すると死亡率が上昇することが分かっているからである。重症度の評価は必須である(Fig. 1)。点数化して評価するのに便利なものとして、APACHEスコアやPitt Bacteremiaスコアがある。重症例であれば、抗菌薬を予測的に投与する必要がある。多剤耐性緑膿菌定着または感染の既往があったり、その時点までのICU滞在期間中にすでに抗菌薬を投与されていたりすると、多剤耐性菌がいつ発生してもおかしくない。一般的には、カルバペネム系薬以外の抗緑膿菌βラクタム系薬が選択されることが多い(Fig. 1, Table 1)。自施設における感受性パターンに基づいて、はじめの予測的投与に用いる抗菌薬を選択しなければならない。過去30日以内にすでに抗緑膿菌βラクタム系薬が投与されている場合は、別の系統の抗緑膿菌抗菌薬を選択する。アミノグリコシド系薬を従とする多剤併用を行う場合は、細菌検査で効果が確認されるか、臨床的に改善が認められれば、アミノグリコシド系薬は3~5日以内に中止するとよいだろう。
CPISスコアは、短期間の単剤投与が適している症例を判別するためのスクリーニングに利用される(Fig. 1)。すでに述べた通り、状態が安定している患者では緑膿菌が分離されても感染ではなくて定着であるに過ぎないことが往々にしてある。CPISスコアを用いれば、悪気はないが無知な関係者が本来必要のない抗緑膿菌薬を投与してしまうのを防ぐことができる。治療開始から丸3日が経過したら、臨床的評価を再度実施すべきである(Fig. 2)。その際には痰培の結果が必要である(Fig. 2)。当初の状態が中等症以下で単剤投与が行われていた症例では、3日間の単剤投与後もCPISが依然として低ければ抗菌薬を中止してもよい。その後は、感染の徴候が出現しないかどうかを注意深く観察する。
コリスチンの投与
多剤耐性緑膿菌の出現をうけ、コリスチンに再び脚光が当たっている(Fig. 2)。ICU肺炎を対象とした対照群のない数編の研究で、コリスチンが有効であるとの結果が得られている。多剤耐性緑膿菌または多剤耐性アシネトバクターによるVAPについての症例対照研究が行われ、イミペネム投与例では72%、コリスチン投与例では75%において臨床的に有効性が認められた。前述の通り、PK/PDに関する研究ではコリスチンは6~8時間おきの投与の方が、12時間おきよりも好ましいことが分かっている。
動物実験およびin vitro研究において、コリスチンとリファンピシン、コリスチンおよびカルバペネムの組み合わせは緑膿菌に対して相乗効果を発揮することが示されている。しかし、ヒトを対象とした研究ではコリスチンを含む多剤併用の有効性を裏付ける結果は得られていない。コリスチンはもとより市販されているあらゆる抗菌薬にin vitroで耐性を示す汎薬剤耐性緑膿菌(PDRP)によるVAP症例も発生している。その主な危険因子はコリスチンとカルバペネムの多剤併用が13日を超えて実施した場合であると報告されている。
コリスチンは可逆性の腎毒性と可逆性の神経毒性を発現することが知られている。しかし、重症患者では色々な異常が入り組んで存在しているため、このような有害作用を薬剤によるものなのかそうでないのかを見極めるのは困難である。コリスチンによる腎毒性は、解決可能な問題である。コリスチンは、腎毒性はあるのに聴神経毒性はない珍しい薬剤である。
教訓 肺に浸潤影がありICU肺炎として治療が行われている患者の50%~70%は、感染以外の原因によって浸潤影を呈しています。感染していないICU患者や、重症ではないICU患者に見境なく抗菌薬を投与すると死亡率が上昇することが分かっています。
2011-07-27 07:19
コメント(0)
緑膿菌肺炎~多剤vs単剤③ [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part II: Antimicrobial Resistance, Pharmacodynamic Concepts, and Antibiotic Therapy
CHEST 2011年5月号より
細菌感染症重症例についての無作為化研究および観測研究を対象としたメタ分析/メタ回帰分析では、敗血症および敗血症性ショックといった極めて重症度の高い症例では、多剤併用の方が転帰が改善することが明らかにされている。このメタ分析の対象研究には、緑膿菌菌血症の研究複数と、緑膿菌によるVAPについての研究2編が含まれている。
Paulらが執筆したコクラン・レビューでは、多剤併用療法には臨床上の有益性があるかどうかはっきりしない一方で、アミノグリコシドを併用すれば腎毒性という欠点がある、と述べられている。アミノグリコシドの腎毒性は、投与期間と相関して発現するということを我々は指摘しておく。好中球減少症患者を対象とした初期の研究では、アミノグリコシドの投与期間は10~14日間であった。緑膿菌菌血症を発症したAIDS患者21名についての研究では、アミノグリコシド投与期間の中央値は12日であった(最長32日)(この研究では、アミノグリコシドと他の抗菌薬の組合せの多剤併用療法が行われた患者の方が単剤投与の患者よりも死亡率が有意に低かった)。発熱を呈する好中球減少症患者604名を対象とした別の研究では、アミカシンまたはトブラマイシンが16.6日間投与された(15.5日~122日)。以上を踏まえると、アミノグリコシドの毒性は投与期間が5日以下のときはほとんどないといってもよいと考えられる。予測的抗菌薬治療として、まずアミノグリコシドを3~5日のみ投与する多剤併用療法を行い、その後単剤投与に移行する方法を行うと、アミノグリコシドの投与期間がこんなに短くても生存率が有意に上昇することをChamotらが報告している。
多剤耐性緑膿菌が出現して以降、緑膿菌肺炎が疑われる重症患者では、単剤投与は力不足になってしまった。肺炎症例でははじめに適切な抗菌薬を選択することが死亡率を低下させる上で死活的に重要である。緑膿菌肺炎の患者では、多剤併用にすれば in vitroで感受性のある抗菌薬が選択される可能性が高くなると考えられる。アミノグリコシド系薬の毒性は、投与期間を短縮すれば低減できる。もしくはアミノグリコシドの毒性が懸念されるのであれば、代わりにキノロン系薬を用いればよい。したがって、緑膿菌肺炎が疑われる症例では、多剤併用を推奨する。多剤耐性緑膿菌が蔓延している病院では、特に多剤併用が望ましい。無作為化試験を行い多剤併用療法の検証を行うことが理想ではあるが、そのような研究を行うためにクリアしなければならないハードルは、ほぼ不可能な壁として我々の前に立ちはだかる。例えば、十分な検出力を確保するには多数の患者を登録する必要があったり、緑膿菌肺炎の確定診断を下すことが難しかったりすることである。
緑膿菌肺炎と推測される症例では、抗緑膿菌βラクタム系薬を中心として抗菌療法を組み立てることを推奨する(Table 1)(PartⅠ「診断」の項で述べた、重症患者以外における定着についての注意事項を念頭に置くこと)。多剤耐性菌が跋扈する現代では、多剤併用によって相加効果や、場合によっては相乗効果が得られる可能性があることを考えると、アミノグリコシド系薬を3~5日併用すると良いであろう。痰の培養で緑膿菌が分離されin vitroの感受性が分かれば、その結果によっては抗菌薬の変更や、アミノグリコシド系薬の中止が可能である。緑膿菌が痰から検出されなければ、それまで使用していた強力な抗菌薬を、よりマイルドなものに変更することができるであろう。
多剤併用療法において主となる抗菌薬に組み合わせる抗菌薬としてキノロン系とアミノグリコシド系のどちらがより効果が高いのかは不明である。この件についての無作為化試験は今のところまだ行われていないが、多くの集中治療専門医は抗緑膿菌βラクタム系薬を主とし、キノロン系薬を従とする組合せを好む。アミノグリコシド系薬を選択すると腎毒性が懸念されるからである。グラム陰性桿菌(緑膿菌を含む)による菌血症についての遡及的研究では、中等症以下の患者においてβラクタム系薬単剤を投与された群よりもβラクタム系薬とキノロン系薬が併用投与された群の方が死亡率が低いという結果が報告されている。
βラクタム系薬二剤の併用は行うべきではない。動物実験では、βラクタム系薬二剤投与は、βラクタム系薬とアミノグリコシド系薬の併用よりも効果が劣ることが明らかにされている。βラクタム系薬を二剤投与すると、緑膿菌感染患者の40%(2/5)において耐性菌が発生したとの報告もある。
抗緑膿菌ペニシリン系薬とアミノグリコシド系薬の二剤併用にさらにリファンピシンを足すと、in vitro実験では緑膿菌に対する相乗効果が得られることが分かっている。また、好中球減少マウスモデルに緑膿菌菌血症を発症させてこの三剤を投与すると生存率が向上することが示されている。従来の多剤併用療法では治療に難渋する緑膿菌感染症例においても、対象数は少数ではあるとはいえこの三剤の組合せが奏功したことが報告されている。緑膿菌菌血症患者121名を対象とした抗緑膿菌βラクタム系薬とアミノグリコシド系薬の併用±リファンピシンについての前向き無作為化試験が行われた。リファンピシンを含む三剤併用群に無作為化割り当てられた患者の方が細菌学的には治療成績が有意に優れていたが、生存率についてはリファンピシンを含まない二剤併用群とのあいだに有意差は認められなかった。多剤耐性緑膿菌肺炎の患者8名中6名において、カルバペネム系薬とホスホマイシンの併用が有効であったと報告されている。
教訓 緑膿菌肺炎と推測される症例では、抗緑膿菌βラクタムに加え、アミノグリコシドまたはキノロンの併用がよさそうです。アミノグリコシドの投与期間は3~5日です。βラクタム二剤併用はだめです。難治例に対して抗緑膿菌ペニシリン系+アミノグリコシド+リファンピシン、多剤耐性緑膿菌肺炎にカルバペネムとホスホマイシンの併用が有効であったという報告があります。
CHEST 2011年5月号より
細菌感染症重症例についての無作為化研究および観測研究を対象としたメタ分析/メタ回帰分析では、敗血症および敗血症性ショックといった極めて重症度の高い症例では、多剤併用の方が転帰が改善することが明らかにされている。このメタ分析の対象研究には、緑膿菌菌血症の研究複数と、緑膿菌によるVAPについての研究2編が含まれている。
Paulらが執筆したコクラン・レビューでは、多剤併用療法には臨床上の有益性があるかどうかはっきりしない一方で、アミノグリコシドを併用すれば腎毒性という欠点がある、と述べられている。アミノグリコシドの腎毒性は、投与期間と相関して発現するということを我々は指摘しておく。好中球減少症患者を対象とした初期の研究では、アミノグリコシドの投与期間は10~14日間であった。緑膿菌菌血症を発症したAIDS患者21名についての研究では、アミノグリコシド投与期間の中央値は12日であった(最長32日)(この研究では、アミノグリコシドと他の抗菌薬の組合せの多剤併用療法が行われた患者の方が単剤投与の患者よりも死亡率が有意に低かった)。発熱を呈する好中球減少症患者604名を対象とした別の研究では、アミカシンまたはトブラマイシンが16.6日間投与された(15.5日~122日)。以上を踏まえると、アミノグリコシドの毒性は投与期間が5日以下のときはほとんどないといってもよいと考えられる。予測的抗菌薬治療として、まずアミノグリコシドを3~5日のみ投与する多剤併用療法を行い、その後単剤投与に移行する方法を行うと、アミノグリコシドの投与期間がこんなに短くても生存率が有意に上昇することをChamotらが報告している。
多剤耐性緑膿菌が出現して以降、緑膿菌肺炎が疑われる重症患者では、単剤投与は力不足になってしまった。肺炎症例でははじめに適切な抗菌薬を選択することが死亡率を低下させる上で死活的に重要である。緑膿菌肺炎の患者では、多剤併用にすれば in vitroで感受性のある抗菌薬が選択される可能性が高くなると考えられる。アミノグリコシド系薬の毒性は、投与期間を短縮すれば低減できる。もしくはアミノグリコシドの毒性が懸念されるのであれば、代わりにキノロン系薬を用いればよい。したがって、緑膿菌肺炎が疑われる症例では、多剤併用を推奨する。多剤耐性緑膿菌が蔓延している病院では、特に多剤併用が望ましい。無作為化試験を行い多剤併用療法の検証を行うことが理想ではあるが、そのような研究を行うためにクリアしなければならないハードルは、ほぼ不可能な壁として我々の前に立ちはだかる。例えば、十分な検出力を確保するには多数の患者を登録する必要があったり、緑膿菌肺炎の確定診断を下すことが難しかったりすることである。
緑膿菌肺炎と推測される症例では、抗緑膿菌βラクタム系薬を中心として抗菌療法を組み立てることを推奨する(Table 1)(PartⅠ「診断」の項で述べた、重症患者以外における定着についての注意事項を念頭に置くこと)。多剤耐性菌が跋扈する現代では、多剤併用によって相加効果や、場合によっては相乗効果が得られる可能性があることを考えると、アミノグリコシド系薬を3~5日併用すると良いであろう。痰の培養で緑膿菌が分離されin vitroの感受性が分かれば、その結果によっては抗菌薬の変更や、アミノグリコシド系薬の中止が可能である。緑膿菌が痰から検出されなければ、それまで使用していた強力な抗菌薬を、よりマイルドなものに変更することができるであろう。
多剤併用療法において主となる抗菌薬に組み合わせる抗菌薬としてキノロン系とアミノグリコシド系のどちらがより効果が高いのかは不明である。この件についての無作為化試験は今のところまだ行われていないが、多くの集中治療専門医は抗緑膿菌βラクタム系薬を主とし、キノロン系薬を従とする組合せを好む。アミノグリコシド系薬を選択すると腎毒性が懸念されるからである。グラム陰性桿菌(緑膿菌を含む)による菌血症についての遡及的研究では、中等症以下の患者においてβラクタム系薬単剤を投与された群よりもβラクタム系薬とキノロン系薬が併用投与された群の方が死亡率が低いという結果が報告されている。
βラクタム系薬二剤の併用は行うべきではない。動物実験では、βラクタム系薬二剤投与は、βラクタム系薬とアミノグリコシド系薬の併用よりも効果が劣ることが明らかにされている。βラクタム系薬を二剤投与すると、緑膿菌感染患者の40%(2/5)において耐性菌が発生したとの報告もある。
抗緑膿菌ペニシリン系薬とアミノグリコシド系薬の二剤併用にさらにリファンピシンを足すと、in vitro実験では緑膿菌に対する相乗効果が得られることが分かっている。また、好中球減少マウスモデルに緑膿菌菌血症を発症させてこの三剤を投与すると生存率が向上することが示されている。従来の多剤併用療法では治療に難渋する緑膿菌感染症例においても、対象数は少数ではあるとはいえこの三剤の組合せが奏功したことが報告されている。緑膿菌菌血症患者121名を対象とした抗緑膿菌βラクタム系薬とアミノグリコシド系薬の併用±リファンピシンについての前向き無作為化試験が行われた。リファンピシンを含む三剤併用群に無作為化割り当てられた患者の方が細菌学的には治療成績が有意に優れていたが、生存率についてはリファンピシンを含まない二剤併用群とのあいだに有意差は認められなかった。多剤耐性緑膿菌肺炎の患者8名中6名において、カルバペネム系薬とホスホマイシンの併用が有効であったと報告されている。
教訓 緑膿菌肺炎と推測される症例では、抗緑膿菌βラクタムに加え、アミノグリコシドまたはキノロンの併用がよさそうです。アミノグリコシドの投与期間は3~5日です。βラクタム二剤併用はだめです。難治例に対して抗緑膿菌ペニシリン系+アミノグリコシド+リファンピシン、多剤耐性緑膿菌肺炎にカルバペネムとホスホマイシンの併用が有効であったという報告があります。
2011-07-26 07:30
コメント(0)
緑膿菌肺炎~多剤vs単剤② [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part II: Antimicrobial Resistance, Pharmacodynamic Concepts, and Antibiotic Therapy
CHEST 2011年5月号より
緑膿菌肺炎患者における多剤併用 vs 単剤投与
多剤併用では、抗菌スペクトラムの拡大、相乗効果、抗菌薬耐性の発生抑制、重複感染の予防といった効果を期待することができる。しかし、多剤併用によって転帰が改善することが示されているものの、確定的ではない。多剤併用によって死亡率が低下することを示す先駆けとなった諸研究で用いられた抗菌薬は、現在ではもう使用されていない。さらに、その大半が菌血症を呈する好中球減少症患者を対象とした研究である。第三世代、第四世代セファロスポリン系薬のような広域スペクトラムの殺菌作用を有する抗菌薬の登場をうけ、アミノグリコシド系薬を併用する必要はないのではないかという意見が示されるようになってきた。
緑膿菌菌血症患者123名を対象にした前向き研究が行われ、多剤併用療法のin vitroでの有効性が検討された。患者に投与した抗菌薬を用いて、チェッカーボード法および時間-殺菌曲線による評価を行った。チェッカーボード法では、相乗効果があるとされている多剤併用療法を行っても死亡率の低下は認められなかった。しかし、時間-殺菌曲線による解析では、相乗効果のある組み合わせの多剤併用を行った場合には死亡率が低下するという結果が得られた:相乗効果のある多剤併用が行われた患者は46%(56/123)が生存したのに対し、相乗効果のない多剤併用(相加効果もしくは単剤の効果と変わらない組み合わせ)が行われた患者は28%(34/123)しか生存しなかった。多剤併用の方が優れているというはっきりした傾向が認められたものの、統計学的な有意差は得られなかった(Fisherの正確検定、両側検定、P=0.10)。
発熱のある好中球減少症患者、グラム陰性菌による菌血症患者および敗血症患者では、多剤併用療法を行っても生存率の改善にはつながらない、という結果が数編のメタ分析で
報告されている。ただ、これらのメタ分析は緑膿菌に特化したものではないという点に十分注意する必要がある。多剤併用によって、腎毒性は観察されるのに、抗菌薬耐性や重複感染の抑制にはつながらないという結果が示されているのはやや意外である。緑膿菌に対する抗菌薬投与についての評価が行われた五編の研究を対象としたメタ分析では、多剤併用療法が行われた患者群では死亡率が低下するとされている。しかし、このメタ分析の対象となった五編のうち四編では、単剤群ではアミノグリコシド一剤のみが投与されていて、緑膿菌菌血症の治療としてはそもそも不適切であると考えられた。
緑膿菌肺炎の患者を対象として単剤投与と多剤併用の有効性を比較した研究はごく少数しか行われていないため、肺炎症例一般について単剤と多剤併用を比較した研究も含めて以下のように検討した。肺炎一般についての9編の研究において、緑膿菌が起因菌であった症例は6.0%~100%を占めた。この9編のうち2編では、多剤併用によって生存率が有意に向上した。肺炎の治療法についての2編の総説で示された結論をまとめた1編の総説が発表されている。2編の総説のうち1編では、院内肺炎の患者を対象とした研究6編、院内肺炎もしくは重症市中肺炎の患者を対象とした研究1編が取り上げられた。もう1編の総説で取り上げられた研究の対象となった院内肺炎患者を全部合わせると計1200名以上であった。以上2編の総説をまとめた総説によると、単剤投与の方が多剤併用よりも治療奏功率が有意に高いことを示した研究が2編あったが、それ以外の研究では単剤投与と多剤併用の治療成績は同等であったと報告されている。計1805例のVAP疑い症例を対象にした臨床試験11編についてのメタ分析が行われ、単剤投与と多剤併用のVAPに対する有効性が比較された。対象患者全体の85.1%に機械的人工呼吸が行われ、緑膿菌を起因菌とするVAPを発症した患者は13.8%を占めた。単剤投与と多剤併用の死亡率および治療失敗率は同等であった。外傷ICUに収容され、BAL検体を用いた定量培養で緑膿菌VAPと診断された患者84名を対象とした前向き研究では、全例で単剤投与による予測的治療が行われたことが分かった。そのうち94.1%において、培養で治療が成功したことが確認された。一方、5.9%の症例においては単剤では治癒に至らず、セフェピムとアミノグリコシドの併用によって治療が成功した。VAPについての研究2編では、多剤併用療法を行っても死亡率は低下しないことが明らかにされている。しかし、抗菌薬投与開始から起因菌に感受性のある薬剤が選択されていた患者の割合は、単剤投与群より多剤併用群の方が有意に高かったし、培養で緑膿菌が分離されなくなった症例の割合も、多剤併用群の方が有意に高かった。緑膿菌またはアシネトバクター属によるVAPを発症した患者を対象に、28ヶ所のICUで行われた前向き研究では、多剤併用と単剤使用とでは効果に差はないことが明らかにされた。だが、適切な抗菌薬療法が行われた(=in vitro検査で感受性が確認されている抗菌薬が選択され、かつ、培養が陰性になる)患者の割合は、多剤併用群の方が有意に高かった。
教訓 多剤併用では、抗菌スペクトラムの拡大、相乗効果、抗菌薬耐性の発生抑制、重複感染の予防といった効果を期待することができますが、多剤併用によって転帰が改善すると言われていますが、はっきりしているわけではありません。緑膿菌肺炎の患者を対象として単剤投与と多剤併用の有効性を比較した研究はあまりありません。
CHEST 2011年5月号より
緑膿菌肺炎患者における多剤併用 vs 単剤投与
多剤併用では、抗菌スペクトラムの拡大、相乗効果、抗菌薬耐性の発生抑制、重複感染の予防といった効果を期待することができる。しかし、多剤併用によって転帰が改善することが示されているものの、確定的ではない。多剤併用によって死亡率が低下することを示す先駆けとなった諸研究で用いられた抗菌薬は、現在ではもう使用されていない。さらに、その大半が菌血症を呈する好中球減少症患者を対象とした研究である。第三世代、第四世代セファロスポリン系薬のような広域スペクトラムの殺菌作用を有する抗菌薬の登場をうけ、アミノグリコシド系薬を併用する必要はないのではないかという意見が示されるようになってきた。
緑膿菌菌血症患者123名を対象にした前向き研究が行われ、多剤併用療法のin vitroでの有効性が検討された。患者に投与した抗菌薬を用いて、チェッカーボード法および時間-殺菌曲線による評価を行った。チェッカーボード法では、相乗効果があるとされている多剤併用療法を行っても死亡率の低下は認められなかった。しかし、時間-殺菌曲線による解析では、相乗効果のある組み合わせの多剤併用を行った場合には死亡率が低下するという結果が得られた:相乗効果のある多剤併用が行われた患者は46%(56/123)が生存したのに対し、相乗効果のない多剤併用(相加効果もしくは単剤の効果と変わらない組み合わせ)が行われた患者は28%(34/123)しか生存しなかった。多剤併用の方が優れているというはっきりした傾向が認められたものの、統計学的な有意差は得られなかった(Fisherの正確検定、両側検定、P=0.10)。
発熱のある好中球減少症患者、グラム陰性菌による菌血症患者および敗血症患者では、多剤併用療法を行っても生存率の改善にはつながらない、という結果が数編のメタ分析で
報告されている。ただ、これらのメタ分析は緑膿菌に特化したものではないという点に十分注意する必要がある。多剤併用によって、腎毒性は観察されるのに、抗菌薬耐性や重複感染の抑制にはつながらないという結果が示されているのはやや意外である。緑膿菌に対する抗菌薬投与についての評価が行われた五編の研究を対象としたメタ分析では、多剤併用療法が行われた患者群では死亡率が低下するとされている。しかし、このメタ分析の対象となった五編のうち四編では、単剤群ではアミノグリコシド一剤のみが投与されていて、緑膿菌菌血症の治療としてはそもそも不適切であると考えられた。
緑膿菌肺炎の患者を対象として単剤投与と多剤併用の有効性を比較した研究はごく少数しか行われていないため、肺炎症例一般について単剤と多剤併用を比較した研究も含めて以下のように検討した。肺炎一般についての9編の研究において、緑膿菌が起因菌であった症例は6.0%~100%を占めた。この9編のうち2編では、多剤併用によって生存率が有意に向上した。肺炎の治療法についての2編の総説で示された結論をまとめた1編の総説が発表されている。2編の総説のうち1編では、院内肺炎の患者を対象とした研究6編、院内肺炎もしくは重症市中肺炎の患者を対象とした研究1編が取り上げられた。もう1編の総説で取り上げられた研究の対象となった院内肺炎患者を全部合わせると計1200名以上であった。以上2編の総説をまとめた総説によると、単剤投与の方が多剤併用よりも治療奏功率が有意に高いことを示した研究が2編あったが、それ以外の研究では単剤投与と多剤併用の治療成績は同等であったと報告されている。計1805例のVAP疑い症例を対象にした臨床試験11編についてのメタ分析が行われ、単剤投与と多剤併用のVAPに対する有効性が比較された。対象患者全体の85.1%に機械的人工呼吸が行われ、緑膿菌を起因菌とするVAPを発症した患者は13.8%を占めた。単剤投与と多剤併用の死亡率および治療失敗率は同等であった。外傷ICUに収容され、BAL検体を用いた定量培養で緑膿菌VAPと診断された患者84名を対象とした前向き研究では、全例で単剤投与による予測的治療が行われたことが分かった。そのうち94.1%において、培養で治療が成功したことが確認された。一方、5.9%の症例においては単剤では治癒に至らず、セフェピムとアミノグリコシドの併用によって治療が成功した。VAPについての研究2編では、多剤併用療法を行っても死亡率は低下しないことが明らかにされている。しかし、抗菌薬投与開始から起因菌に感受性のある薬剤が選択されていた患者の割合は、単剤投与群より多剤併用群の方が有意に高かったし、培養で緑膿菌が分離されなくなった症例の割合も、多剤併用群の方が有意に高かった。緑膿菌またはアシネトバクター属によるVAPを発症した患者を対象に、28ヶ所のICUで行われた前向き研究では、多剤併用と単剤使用とでは効果に差はないことが明らかにされた。だが、適切な抗菌薬療法が行われた(=in vitro検査で感受性が確認されている抗菌薬が選択され、かつ、培養が陰性になる)患者の割合は、多剤併用群の方が有意に高かった。
教訓 多剤併用では、抗菌スペクトラムの拡大、相乗効果、抗菌薬耐性の発生抑制、重複感染の予防といった効果を期待することができますが、多剤併用によって転帰が改善すると言われていますが、はっきりしているわけではありません。緑膿菌肺炎の患者を対象として単剤投与と多剤併用の有効性を比較した研究はあまりありません。
2011-07-25 07:17
コメント(0)
緑膿菌肺炎~多剤vs単剤① [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part II: Antimicrobial Resistance, Pharmacodynamic Concepts, and Antibiotic Therapy
CHEST 2011年5月号より
抗菌薬の投与
肺炎を発症した入院患者に対し、時機を逸することなく適切な抗菌薬の予測的投与を開始すると死亡率が低下すると考えられている。この件につき、17編の論文を検討した。内訳は、ICU患者のVAPについての研究が14編、全身感染症についての研究が1編、菌血症患者を対象とした研究が2編であった。後二者の計3編では、対象患者の16.0%~62.7%が肺炎であり、肺炎の起因菌が緑膿菌であった症例の占める割合は、14.4%~100%であった(Table 4)。検討した17編のうち10編では、適切な抗菌薬の予測的投与を遅滞なく開始すると、肺炎入院患者の死亡率が有意に低下するという結果が得られた。残りの7編では死亡率の低下にはつながらないと報告されている。
死亡率の低下を示すことができなかった七編のうち、緑膿菌菌血症についての研究一編およびVAPについての研究二編の計三編の著者らは、適切な抗菌薬の予測的投与を直ちに開始しても追いつかないほど対象症例の感染が重篤で、急速に死に至ってしまったとしている。残り四編のうち、三編では統計学的検出力が不足していたことが有意差が認められなかった原因であると述べられ、あとの一編ではこのことについての考察は示されていなかった。
緑膿菌によりVAPや菌血症では、抗菌薬の予測的投与が適切に行われても死亡率は実に3.6%~40.2%と高く、不適切な予測的抗菌薬投与が行われた場合には死亡率はさらに上昇し、17.6%~81.6%にものぼる。そして、当初選択した抗菌薬が不適切であることが分かり、48~72時間後に感受性のある抗菌薬に変更しても死亡率は低下しない。分離された細菌が予測的投与に用いられた抗菌薬に対して耐性があった、というのが不適切な予測的抗菌薬治療の最もよくあるパターンであり、18%~75.0%を占める。緑膿菌は代表的な抗菌薬耐性グラム陰性菌である。
多剤併用 vs 単剤投与
抗菌薬の多剤併用についてのin vitro研究では、アミノグリコシド系薬と抗緑膿菌ペニシリン系薬を併用した場合に相乗効果が得られる可能性が最も高い(~90%)ことが明らかにされている。次いで高い順に、セファロスポリン系薬との併用(~80%)、カルバペネム系薬との併用(~50%)と続く。フルオロキノロン系薬と、βラクタム系またはアミノグリコシド系薬を併用したときに通常得られる効果は、相加効果もしくは単剤のときとあまり変わらない効果である。キノロン系薬と抗緑膿菌βラクタム系薬を併用すると、殺菌能の大部分はβラクタム系薬が担うことになる。薬力学モデルでは、レボフロキサシンとメロペネムを併用すると相乗効果が得られ(3 log cell kill;死ぬ細菌数の対数値が3、つまり10の3乗レベル)、耐性の発生を抑制する効果も高いことが明らかにされている。緑膿菌肺炎の確定診断例では、いずれのキノロン系薬であっても単剤使用は推奨されない。なぜなら、耐性菌が発生する可能性が高く(38%)、十分な殺菌能が得られないことが多い(67%)からである。レボフロキサシンにしてもシプロフロキサシンにしても、24時間血中濃度-時間曲線下面積(AUC)/MIC比の目標値>100を達成する可能性が低いことからもこのことが裏付けられる。
動物モデルにおける多剤併用
動物実験で緑膿菌肺炎に対する多剤併用療法の効果が検討されている。渉猟の結果、モルモットを使用したものが四編、マウスを用いた研究が二編あった。以上六編のうち二編ではシクロフォスファミド投与により好中球減少症モデルが作成された。三編ではムコイド型緑膿菌が使用された。四編で緑膿菌を経鼻接種して肺炎モデルが作成され、経気管的に接種した研究が二編あった。五編において死亡率がエンドポイントとして設定された。さらに、三編では肺からの緑膿菌除去率が報告された。多剤併用療法によって死亡率が有意に低下するという結果を示した研究が二編、死亡率が低下する傾向があることを示した研究が二編存在した。セフタジジムとクラリスロマイシンの併用は、セフタジジム単剤またはクラリスロマイシン単剤よりも優れた効果を発揮した。セフスロジンとトブラマイシンを併用すると、βラクタム単剤の場合よりは死亡率が低下するが、トブラマイシン単剤単剤の場合とは差がない。セフタジジムとトブラマイシンを併用すると、それぞれ単剤のときよりも有効性が高い傾向が認められたが、有意差はないことが一編の研究で明らかにされている。Rusnakらの研究では、四パターンの併用療法(チカルシリン+トブラマイシン、セフタジジム+トブラマイシン、アズロシリン+トブラマイシン、セフタジジム+メチシリン)がin vitroで相乗効果を示すことが示されている。しかし、以上のいずれの併用パターンも、単剤療法(アズロシリン、セフタジジムのみ、トブラマイシン、メチシリン)と比べて死亡率を有意に低下させる効果はない。肺組織から細菌が駆除される程度について、三編の研究で検討が行われた。セフスロジンとトブラマイシンを併用しても駆除率は改善しないという結果が一編で示された。セフタジジムとトブラマイシンを併用すると、駆除率が上昇することが分かった。メズロシリンとトブラマイシンを好中球減少症モデル動物に投与すると緑膿菌駆除率が上昇するが、好中球減少症ではない実験動物に投与した場合には駆除率に変化は認められなかった。
教訓 緑膿菌によるVAPや菌血症は、抗菌薬の予測的投与が適切に行われても死亡率は3.6%~40.2%、不適切な予測的抗菌薬投与が行われた場合の死亡率は17.6%~81.6%です。当初選択した抗菌薬が不適切であることが分かり、48~72時間後に感受性のある抗菌薬に変更しても死亡率は低下しません。in vitro研究では、アミノグリコシド系薬と抗緑膿菌ペニシリン系薬を併用した場合に相乗効果が得られる可能性が最も高い(~90%)ことが明らかにされています。
CHEST 2011年5月号より
抗菌薬の投与
肺炎を発症した入院患者に対し、時機を逸することなく適切な抗菌薬の予測的投与を開始すると死亡率が低下すると考えられている。この件につき、17編の論文を検討した。内訳は、ICU患者のVAPについての研究が14編、全身感染症についての研究が1編、菌血症患者を対象とした研究が2編であった。後二者の計3編では、対象患者の16.0%~62.7%が肺炎であり、肺炎の起因菌が緑膿菌であった症例の占める割合は、14.4%~100%であった(Table 4)。検討した17編のうち10編では、適切な抗菌薬の予測的投与を遅滞なく開始すると、肺炎入院患者の死亡率が有意に低下するという結果が得られた。残りの7編では死亡率の低下にはつながらないと報告されている。
死亡率の低下を示すことができなかった七編のうち、緑膿菌菌血症についての研究一編およびVAPについての研究二編の計三編の著者らは、適切な抗菌薬の予測的投与を直ちに開始しても追いつかないほど対象症例の感染が重篤で、急速に死に至ってしまったとしている。残り四編のうち、三編では統計学的検出力が不足していたことが有意差が認められなかった原因であると述べられ、あとの一編ではこのことについての考察は示されていなかった。
緑膿菌によりVAPや菌血症では、抗菌薬の予測的投与が適切に行われても死亡率は実に3.6%~40.2%と高く、不適切な予測的抗菌薬投与が行われた場合には死亡率はさらに上昇し、17.6%~81.6%にものぼる。そして、当初選択した抗菌薬が不適切であることが分かり、48~72時間後に感受性のある抗菌薬に変更しても死亡率は低下しない。分離された細菌が予測的投与に用いられた抗菌薬に対して耐性があった、というのが不適切な予測的抗菌薬治療の最もよくあるパターンであり、18%~75.0%を占める。緑膿菌は代表的な抗菌薬耐性グラム陰性菌である。
多剤併用 vs 単剤投与
抗菌薬の多剤併用についてのin vitro研究では、アミノグリコシド系薬と抗緑膿菌ペニシリン系薬を併用した場合に相乗効果が得られる可能性が最も高い(~90%)ことが明らかにされている。次いで高い順に、セファロスポリン系薬との併用(~80%)、カルバペネム系薬との併用(~50%)と続く。フルオロキノロン系薬と、βラクタム系またはアミノグリコシド系薬を併用したときに通常得られる効果は、相加効果もしくは単剤のときとあまり変わらない効果である。キノロン系薬と抗緑膿菌βラクタム系薬を併用すると、殺菌能の大部分はβラクタム系薬が担うことになる。薬力学モデルでは、レボフロキサシンとメロペネムを併用すると相乗効果が得られ(3 log cell kill;死ぬ細菌数の対数値が3、つまり10の3乗レベル)、耐性の発生を抑制する効果も高いことが明らかにされている。緑膿菌肺炎の確定診断例では、いずれのキノロン系薬であっても単剤使用は推奨されない。なぜなら、耐性菌が発生する可能性が高く(38%)、十分な殺菌能が得られないことが多い(67%)からである。レボフロキサシンにしてもシプロフロキサシンにしても、24時間血中濃度-時間曲線下面積(AUC)/MIC比の目標値>100を達成する可能性が低いことからもこのことが裏付けられる。
動物モデルにおける多剤併用
動物実験で緑膿菌肺炎に対する多剤併用療法の効果が検討されている。渉猟の結果、モルモットを使用したものが四編、マウスを用いた研究が二編あった。以上六編のうち二編ではシクロフォスファミド投与により好中球減少症モデルが作成された。三編ではムコイド型緑膿菌が使用された。四編で緑膿菌を経鼻接種して肺炎モデルが作成され、経気管的に接種した研究が二編あった。五編において死亡率がエンドポイントとして設定された。さらに、三編では肺からの緑膿菌除去率が報告された。多剤併用療法によって死亡率が有意に低下するという結果を示した研究が二編、死亡率が低下する傾向があることを示した研究が二編存在した。セフタジジムとクラリスロマイシンの併用は、セフタジジム単剤またはクラリスロマイシン単剤よりも優れた効果を発揮した。セフスロジンとトブラマイシンを併用すると、βラクタム単剤の場合よりは死亡率が低下するが、トブラマイシン単剤単剤の場合とは差がない。セフタジジムとトブラマイシンを併用すると、それぞれ単剤のときよりも有効性が高い傾向が認められたが、有意差はないことが一編の研究で明らかにされている。Rusnakらの研究では、四パターンの併用療法(チカルシリン+トブラマイシン、セフタジジム+トブラマイシン、アズロシリン+トブラマイシン、セフタジジム+メチシリン)がin vitroで相乗効果を示すことが示されている。しかし、以上のいずれの併用パターンも、単剤療法(アズロシリン、セフタジジムのみ、トブラマイシン、メチシリン)と比べて死亡率を有意に低下させる効果はない。肺組織から細菌が駆除される程度について、三編の研究で検討が行われた。セフスロジンとトブラマイシンを併用しても駆除率は改善しないという結果が一編で示された。セフタジジムとトブラマイシンを併用すると、駆除率が上昇することが分かった。メズロシリンとトブラマイシンを好中球減少症モデル動物に投与すると緑膿菌駆除率が上昇するが、好中球減少症ではない実験動物に投与した場合には駆除率に変化は認められなかった。
教訓 緑膿菌によるVAPや菌血症は、抗菌薬の予測的投与が適切に行われても死亡率は3.6%~40.2%、不適切な予測的抗菌薬投与が行われた場合の死亡率は17.6%~81.6%です。当初選択した抗菌薬が不適切であることが分かり、48~72時間後に感受性のある抗菌薬に変更しても死亡率は低下しません。in vitro研究では、アミノグリコシド系薬と抗緑膿菌ペニシリン系薬を併用した場合に相乗効果が得られる可能性が最も高い(~90%)ことが明らかにされています。
2011-07-22 07:35
コメント(0)
緑膿菌肺炎~PK/PD [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part II: Antimicrobial Resistance, Pharmacodynamic Concepts, and Antibiotic Therapy
CHEST 2011年5月号より
PK/PDを考える
アミノグリコシド系薬は、濃度依存性に効果をもたらす抗菌薬である。このタイプの抗菌薬は、濃度がMIC(最小発育阻止濃度)の10倍以上のときに殺菌能力を最大限に発揮する。致死量の細菌を投与して作成した感染モデル動物は、アミノグリコシド系薬の一日量を三分割して8時間おきに投与するよりも、一日分を一回で投与する方が生存率が高いことが分かっている。一方、βラクタム系薬は時間依存性に効果をもたらす抗菌薬である。このタイプの抗菌薬は持続投与すると、薬力学の概念である最小発育阻止濃度超過時間(time above MIC)を最大化することができる。一日一回投与や持続投与は、調剤コストの削減にも寄与する。
βラクタム系薬を持続投与したときと間欠投与したときの臨床効果の比較についての研究は少なくとも七編が発表されている(Table 3)。そのうち五編では緑膿菌肺炎の患者が対象として含まれ、全対象患者に占める割合は13%(4/31)から53.1%(103/194)であった。この五編で用いられた薬剤は、ピペラシリン/タゾバクタム、イミペネム/シラスタチン、メロペネムおよびセフタジジムであった。死亡率および治療転帰(治癒、改善、治療失敗)が臨床効果の評価項目とされた。持続投与の方が高い有効性を得られるという結果を示した研究は二編で、三編では有意差なしという結果が得られた。七編のうち残りの二編では、起因菌や感染部位が明示されていなかったが、持続投与の方が転帰が良かった。薬力学的な目標値を達成するには、間欠投与より持続投与の方が優れていることが示されている。したがって、緑膿菌肺炎の症例では抗緑膿菌βラクタム系薬を持続投与することを積極的に考慮すべきである。
抗緑膿菌抗菌薬の中でもメロペネムやドリペネム関しては、静脈内投与にかける時間を一時間から四時間に延長する簡単な方法が試みられている。投与間隔が何時間であろうが、一回の投与にかける時間を延ばせば最小発育阻止濃度超過時間(time above MIC)も増加するので、高いMICを要する細菌の根絶には適している。ドリペネムはin vitroでは緑膿菌に対して最も強力な効果を示すカルバペネム系薬である。人工呼吸器関連肺炎(VAP)患者531名を対象としてドリペネムとイミペネムの効果を比較した前向き無作為化試験では、イミペネム群よりドリペネム群の方が緑膿菌肺炎患者の臨床的および微生物学的治癒率が高い傾向が認められたが、統計学的な有意差はなかった。
ポリミキシンも濃度依存性に抗菌活性を発揮する。感染動物モデルでは血中濃度-時間曲線下面積(AUC)が抗菌活性を予測するのに最適な指標であることが分かっている。ポリミキシンが濃度依存性に直ちに殺菌能を示し、軽度ではない接種効果(細菌量が増えるとMICもそれにしたがって上昇すること)を伴うことがtime-kill試験で確認されている。ポリミキシンには逆PAE(negative postantibiotic effect)という他に類のない作用がある。ポリミキシン投与後にポリミキシン濃度が緑膿菌に対するMICを下回ると、2~6時間にわたり緑膿菌の増殖能が大幅に増加するのである。ポリミキシン感受性の株がいなくなってポリミキシン耐性株が取って代わって急速に増殖することが原因である。コリスチンは一日三回投与だと耐性菌の発生を最大限抑制することができることが薬力学モデルで示されている。したがって、コリスチンは6~8時間おきに投与するのが望ましい。
教訓 緑膿菌肺炎の症例では抗緑膿菌βラクタム系薬を持続投与することを積極的に考慮します。アミノグリコシドは一日一回です。コリスチンは一日三回です。
CHEST 2011年5月号より
PK/PDを考える
アミノグリコシド系薬は、濃度依存性に効果をもたらす抗菌薬である。このタイプの抗菌薬は、濃度がMIC(最小発育阻止濃度)の10倍以上のときに殺菌能力を最大限に発揮する。致死量の細菌を投与して作成した感染モデル動物は、アミノグリコシド系薬の一日量を三分割して8時間おきに投与するよりも、一日分を一回で投与する方が生存率が高いことが分かっている。一方、βラクタム系薬は時間依存性に効果をもたらす抗菌薬である。このタイプの抗菌薬は持続投与すると、薬力学の概念である最小発育阻止濃度超過時間(time above MIC)を最大化することができる。一日一回投与や持続投与は、調剤コストの削減にも寄与する。
βラクタム系薬を持続投与したときと間欠投与したときの臨床効果の比較についての研究は少なくとも七編が発表されている(Table 3)。そのうち五編では緑膿菌肺炎の患者が対象として含まれ、全対象患者に占める割合は13%(4/31)から53.1%(103/194)であった。この五編で用いられた薬剤は、ピペラシリン/タゾバクタム、イミペネム/シラスタチン、メロペネムおよびセフタジジムであった。死亡率および治療転帰(治癒、改善、治療失敗)が臨床効果の評価項目とされた。持続投与の方が高い有効性を得られるという結果を示した研究は二編で、三編では有意差なしという結果が得られた。七編のうち残りの二編では、起因菌や感染部位が明示されていなかったが、持続投与の方が転帰が良かった。薬力学的な目標値を達成するには、間欠投与より持続投与の方が優れていることが示されている。したがって、緑膿菌肺炎の症例では抗緑膿菌βラクタム系薬を持続投与することを積極的に考慮すべきである。
抗緑膿菌抗菌薬の中でもメロペネムやドリペネム関しては、静脈内投与にかける時間を一時間から四時間に延長する簡単な方法が試みられている。投与間隔が何時間であろうが、一回の投与にかける時間を延ばせば最小発育阻止濃度超過時間(time above MIC)も増加するので、高いMICを要する細菌の根絶には適している。ドリペネムはin vitroでは緑膿菌に対して最も強力な効果を示すカルバペネム系薬である。人工呼吸器関連肺炎(VAP)患者531名を対象としてドリペネムとイミペネムの効果を比較した前向き無作為化試験では、イミペネム群よりドリペネム群の方が緑膿菌肺炎患者の臨床的および微生物学的治癒率が高い傾向が認められたが、統計学的な有意差はなかった。
ポリミキシンも濃度依存性に抗菌活性を発揮する。感染動物モデルでは血中濃度-時間曲線下面積(AUC)が抗菌活性を予測するのに最適な指標であることが分かっている。ポリミキシンが濃度依存性に直ちに殺菌能を示し、軽度ではない接種効果(細菌量が増えるとMICもそれにしたがって上昇すること)を伴うことがtime-kill試験で確認されている。ポリミキシンには逆PAE(negative postantibiotic effect)という他に類のない作用がある。ポリミキシン投与後にポリミキシン濃度が緑膿菌に対するMICを下回ると、2~6時間にわたり緑膿菌の増殖能が大幅に増加するのである。ポリミキシン感受性の株がいなくなってポリミキシン耐性株が取って代わって急速に増殖することが原因である。コリスチンは一日三回投与だと耐性菌の発生を最大限抑制することができることが薬力学モデルで示されている。したがって、コリスチンは6~8時間おきに投与するのが望ましい。
教訓 緑膿菌肺炎の症例では抗緑膿菌βラクタム系薬を持続投与することを積極的に考慮します。アミノグリコシドは一日一回です。コリスチンは一日三回です。
2011-07-21 07:46
コメント(0)
緑膿菌肺炎~抗菌薬耐性② [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part II: Antimicrobial Resistance, Pharmacodynamic Concepts, and Antibiotic Therapy
CHEST 2011年5月号より
ESBLを産生する緑膿菌にはカルバペネム系薬を選択する。大半のESBLはカルバペネム系薬を不活化しないからである。転移することのできるβラクタマーゼ、例えばメタロ酵素は、亜鉛イオンがないと活性化しない(いわゆるクラスBβラクタマーゼ)。このようなβラクタマーゼは、クラブラン酸やスルバクタムなどのβラクタマーゼ阻害剤の影響を受けず、さらにはセファロスポリンやカルバペネムを加水分解する作用さえ備えている。以上のような特徴を持つメタロ酵素が出現してからというもの、カルバペネム耐性緑膿菌が占める割合が増加している。緑膿菌の産生するカルバペネマーゼの代表格がVIM-2である。緑膿菌が元来持っている内因性セファロスポリナーゼによってイミペネムに対する耐性が発現することがある。βラクタマーゼにはいろいろな略語が当てられているが、標準的もしくは理論的な体系に従った表現ではない。本来の科学的命名法による名称は、この分野の研究者にしか理解できないものになっている。
排出ポンプ機構がはたらくと、抗菌薬が標的部位に接触する間もなく菌体外へ除去されてしまう(Table 2)。Mex AB-OprMは最も強力な排出ポンプで、キノロン系薬、抗緑膿菌ペニシリン系薬および第三世代セファロスポリン系薬に対する耐性をもたらす。
緑膿菌のアミノグリコシド耐性は多くの場合アミノグリコシド修飾酵素の作用によって出現する。そのなかで最もよく見られるのが、アセチルトランスフェラーゼである。アミノグリコシドの分子構造が酵素によって修飾されると、緑膿菌リボゾームとのアミノグリコシドの結合力が低下する。アミカシンはアミノグリコシド系薬のなかで酵素による修飾を最も受けにくい薬剤である。アミカシンには複数の酵素が作用しないと、緑膿菌リボゾームとの結合力に変化が生じないからである。アミノグリコシド系薬の菌体内取り込みが低下すると、アミカシンを含めあらゆるアミノグリコシド系薬に対する耐性が生ずる。新しいアミノグリコシド耐性遺伝子カセットが解明されつつあり、最悪のケースでは、これらの遺伝子カセットはメタロ酵素をエンコードするインテグロンに取り込まれている。
細菌のDNAジャイレースは、細菌染色体の超らせん(スーパーコイル)構造を維持したり、複製の過程で生じたDNAの損傷を修復したりする。キノロン系薬はDNAジャイレースの活性を阻害することによって抗菌活性を発揮する。DNAジャイレースが不活化されると、DNA複製が滞り細胞死に至る。DNAジャイレースに変異が起こると、キノロン耐性が出現する。シプロフロキサシンとレボフロキサシンは抗緑膿菌キノロンと呼ばれ、in vitroではある程度の抗緑膿菌活性を示すが、βラクタム系と比べると効果が劣る。肺炎球菌はキノロン系薬によって速やかに死滅するが、緑膿菌は肺炎球菌よりも長時間曝露されていないとキノロン系薬によっては死なない。
外膜透過性低下が抗菌薬耐性をもたらすことがある。複数の異なる系統の抗菌薬が、この機序によって効果を発揮できなくなる(Table 2)。緑膿菌がカルバペネム耐性化する機序のうちもっとも一般的なのは、遺伝子変異による外膜タンパク(OprD)の欠失である。イミペネム投与中には、遺伝子変異が起こりOprDが喪失することは珍しくない。つまり、緑膿菌感染症に対しイミペネムを投与していると、緑膿菌がイミペネム耐性を保有するようになるのである。幸い、OprDがない緑膿菌はカルバペネム以外のβラクタム系薬には耐性を示さない。
緑膿菌がコリスチン耐性を示すことはほとんどない。コリスチン耐性緑膿菌は、コリスチン吸入療法を実施している繊維性嚢胞症の患者から検出される例が大部分を占めている。緑膿菌のコリスチンに対する高度耐性は、外膜の構造が変化することによって出現する。ICUでは多剤耐性緑膿菌は、肺炎患者から分離されることが多く、この分離株はコリスチンにのみin vitroでの感受性を示す。汎薬剤耐性(PDR)緑膿菌は、コリスチンはもちろんのこと、市販される抗菌薬のすべてに対する耐性を持つ緑膿菌である。病原菌は耐性を獲得すると、通常は毒性が低下する(適応仮説)。しかし、多剤耐性緑膿菌(MDRP)についての基礎研究では、毒性が低下するという報告もあれば、変化しないという報告もある。
教訓 ESBLを産生する緑膿菌にはカルバペネム系薬を選択しますが、メタロ酵素を持つカルバペネム耐性緑膿菌が占める割合が増加しています。シプロフロキサシンとレボフロキサシンは抗緑膿菌キノロンと呼ばれていますが、βラクタム系と比べると効果が劣ります。
CHEST 2011年5月号より
ESBLを産生する緑膿菌にはカルバペネム系薬を選択する。大半のESBLはカルバペネム系薬を不活化しないからである。転移することのできるβラクタマーゼ、例えばメタロ酵素は、亜鉛イオンがないと活性化しない(いわゆるクラスBβラクタマーゼ)。このようなβラクタマーゼは、クラブラン酸やスルバクタムなどのβラクタマーゼ阻害剤の影響を受けず、さらにはセファロスポリンやカルバペネムを加水分解する作用さえ備えている。以上のような特徴を持つメタロ酵素が出現してからというもの、カルバペネム耐性緑膿菌が占める割合が増加している。緑膿菌の産生するカルバペネマーゼの代表格がVIM-2である。緑膿菌が元来持っている内因性セファロスポリナーゼによってイミペネムに対する耐性が発現することがある。βラクタマーゼにはいろいろな略語が当てられているが、標準的もしくは理論的な体系に従った表現ではない。本来の科学的命名法による名称は、この分野の研究者にしか理解できないものになっている。
排出ポンプ機構がはたらくと、抗菌薬が標的部位に接触する間もなく菌体外へ除去されてしまう(Table 2)。Mex AB-OprMは最も強力な排出ポンプで、キノロン系薬、抗緑膿菌ペニシリン系薬および第三世代セファロスポリン系薬に対する耐性をもたらす。
緑膿菌のアミノグリコシド耐性は多くの場合アミノグリコシド修飾酵素の作用によって出現する。そのなかで最もよく見られるのが、アセチルトランスフェラーゼである。アミノグリコシドの分子構造が酵素によって修飾されると、緑膿菌リボゾームとのアミノグリコシドの結合力が低下する。アミカシンはアミノグリコシド系薬のなかで酵素による修飾を最も受けにくい薬剤である。アミカシンには複数の酵素が作用しないと、緑膿菌リボゾームとの結合力に変化が生じないからである。アミノグリコシド系薬の菌体内取り込みが低下すると、アミカシンを含めあらゆるアミノグリコシド系薬に対する耐性が生ずる。新しいアミノグリコシド耐性遺伝子カセットが解明されつつあり、最悪のケースでは、これらの遺伝子カセットはメタロ酵素をエンコードするインテグロンに取り込まれている。
細菌のDNAジャイレースは、細菌染色体の超らせん(スーパーコイル)構造を維持したり、複製の過程で生じたDNAの損傷を修復したりする。キノロン系薬はDNAジャイレースの活性を阻害することによって抗菌活性を発揮する。DNAジャイレースが不活化されると、DNA複製が滞り細胞死に至る。DNAジャイレースに変異が起こると、キノロン耐性が出現する。シプロフロキサシンとレボフロキサシンは抗緑膿菌キノロンと呼ばれ、in vitroではある程度の抗緑膿菌活性を示すが、βラクタム系と比べると効果が劣る。肺炎球菌はキノロン系薬によって速やかに死滅するが、緑膿菌は肺炎球菌よりも長時間曝露されていないとキノロン系薬によっては死なない。
外膜透過性低下が抗菌薬耐性をもたらすことがある。複数の異なる系統の抗菌薬が、この機序によって効果を発揮できなくなる(Table 2)。緑膿菌がカルバペネム耐性化する機序のうちもっとも一般的なのは、遺伝子変異による外膜タンパク(OprD)の欠失である。イミペネム投与中には、遺伝子変異が起こりOprDが喪失することは珍しくない。つまり、緑膿菌感染症に対しイミペネムを投与していると、緑膿菌がイミペネム耐性を保有するようになるのである。幸い、OprDがない緑膿菌はカルバペネム以外のβラクタム系薬には耐性を示さない。
緑膿菌がコリスチン耐性を示すことはほとんどない。コリスチン耐性緑膿菌は、コリスチン吸入療法を実施している繊維性嚢胞症の患者から検出される例が大部分を占めている。緑膿菌のコリスチンに対する高度耐性は、外膜の構造が変化することによって出現する。ICUでは多剤耐性緑膿菌は、肺炎患者から分離されることが多く、この分離株はコリスチンにのみin vitroでの感受性を示す。汎薬剤耐性(PDR)緑膿菌は、コリスチンはもちろんのこと、市販される抗菌薬のすべてに対する耐性を持つ緑膿菌である。病原菌は耐性を獲得すると、通常は毒性が低下する(適応仮説)。しかし、多剤耐性緑膿菌(MDRP)についての基礎研究では、毒性が低下するという報告もあれば、変化しないという報告もある。
教訓 ESBLを産生する緑膿菌にはカルバペネム系薬を選択しますが、メタロ酵素を持つカルバペネム耐性緑膿菌が占める割合が増加しています。シプロフロキサシンとレボフロキサシンは抗緑膿菌キノロンと呼ばれていますが、βラクタム系と比べると効果が劣ります。
2011-07-20 07:09
コメント(0)
緑膿菌肺炎~抗菌薬耐性① [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part II: Antimicrobial Resistance, Pharmacodynamic Concepts, and Antibiotic Therapy
CHEST 2011年5月号より
緑膿菌は抗菌薬耐性を獲得する能力が高く、数多くの耐性機構を装備している悪質な細菌である。緑膿菌肺炎の死亡率は高い。治療には極めて難渋する。本総説では、抗菌薬耐性の疫学、緑膿菌の耐性機構、抗緑膿菌活性の高い抗菌薬および抗緑膿菌βラクタム薬の薬物動態/薬力学(PK/PD)について詳述する。また、多剤併用療法の利点と、コリスチンや抗菌薬エアロゾル製剤の適応についても紹介する。
抗菌療法
全国調査によると、緑膿菌株の70%以上に対して抗菌活性を持つ抗菌薬は、アミノグリコシド系薬、抗緑膿菌ペニシリン系薬、抗緑膿菌セファロスポリン系薬およびカルバペネムである(Table 1)。モノバクタム系薬のアズトレオナムは抗緑膿菌セファロスポリン系薬と同じような抗緑膿菌活性を発揮するが、あまり選択されない。その主な理由は、グラム陽性菌および嫌気性菌といった緑膿菌と同時に分離されることの多い細菌に対する活性が低いからである。抗緑膿菌薬と考えられているキノロン系薬は二種類ある。シプロフロキサシンとレボフロキサシンである(Table 1)。シプロフロキサシンのMIC(0.5mcg/mL)はレボフロキサシンのMIC(1.0mcg/mL)より低く、シプロフロキサシンの方がやや強力なように思われるものの、血中および組織移行性がレボフロキサシンより低いため、この程度の差は帳消しになってしまう。つまり、この二剤の抗緑膿菌活性はほぼ同等ということになる。
耐性の疫学
緑膿菌の抗菌薬耐性はどんどん進化している(Table 2)。米国で行われた三件の大規模調査で過去9~13年のあいだに、フルオロキノロン耐性(15%→40%)、第三世代セファロスポリン耐性(15%→32%)およびカルバペネム耐性(13%→23%)を示す緑膿菌が増えていることが明らかになっている。分離される緑膿菌は、57%~67%が気道検体のものである。
ICUに収容されている気管挿管患者では、抗緑膿菌抗菌薬の投与開始から10日以内に多剤耐性緑膿菌が検出されることがある。交叉耐性が見られることも珍しくない。例えば、ピペラシリン耐性緑膿菌およびシプロフロキサシン耐性緑膿菌は、それぞれピペラシリン感受性緑膿菌およびシプロフロキサシン緑膿菌と比べ、他の系統の緑膿菌にも耐性を示す頻度が高いことが分かっている。
抗菌薬耐性
緑膿菌は、院内肺炎の原因となる多剤耐性グラム陰性桿菌の代表格である。緑膿菌の抗菌薬耐性(自然耐性)発現には少なくとも5通りの機構が関与している。さらに、抗菌薬耐性(獲得耐性)をエンコードする遺伝子を獲得することもできる。主要な耐性化機構は以下の三つである:βラクタマーゼの産生、外膜タンパクの欠損および薬剤排出ポンプのアップレギュレーション(Table 2)。ジャイレースの変異および酵素の不活化は、それぞれキノロン系薬およびアミノグリコシド系薬に特異的な耐性化機構である。以上の耐性化機構は、一つの細菌に同時に複数が存在することがある。これが多剤耐性化の正体である。
緑膿菌は色々な種類のβラクタマーゼを作りだし、広く拡散したり、思いがけない耐性パターンが出現したりすることになる。緑膿菌が産生するβラクタマーゼのうち、AmpC遺伝子が産生するものが大部分を占める。このβラクタマーゼには、様々な抗緑膿菌抗菌薬によって「誘導される」という特性があるため、耐性化に拍車がかかる。AmpC βラクタマーゼは菌体内からの調節によって抑制される。ある種の抗菌薬に曝露されて変異した緑膿菌は、大量のAmpC βラクタマーゼを産生するようになる。このような「脱抑制」化した変異株には、第三世代セファロスポリン系薬およびチカルシリン/クラブラン酸が選択される。基質特異性拡張型βラクタマーゼ(ESBL; extended-spectrum β-lactamase)は、第三世代セファロスポリン系薬、抗緑膿菌ペニシリン系薬および第一世代、第二世代セファロスポリン系薬を加水分解する働きを持つ(Table 1)。ESBL獲得には、配列挿入、トランスポゾンおよびインテグロンなどの遺伝的機構が関わっている。
教訓 緑膿菌が産生するβラクタマーゼには、様々な抗緑膿菌抗菌薬によって「誘導される」という性質があります。ESBLは第三世代セファロスポリン系薬、抗緑膿菌ペニシリン系薬および第一世代、第二世代セファロスポリン系薬を加水分解します。
CHEST 2011年5月号より
緑膿菌は抗菌薬耐性を獲得する能力が高く、数多くの耐性機構を装備している悪質な細菌である。緑膿菌肺炎の死亡率は高い。治療には極めて難渋する。本総説では、抗菌薬耐性の疫学、緑膿菌の耐性機構、抗緑膿菌活性の高い抗菌薬および抗緑膿菌βラクタム薬の薬物動態/薬力学(PK/PD)について詳述する。また、多剤併用療法の利点と、コリスチンや抗菌薬エアロゾル製剤の適応についても紹介する。
抗菌療法
全国調査によると、緑膿菌株の70%以上に対して抗菌活性を持つ抗菌薬は、アミノグリコシド系薬、抗緑膿菌ペニシリン系薬、抗緑膿菌セファロスポリン系薬およびカルバペネムである(Table 1)。モノバクタム系薬のアズトレオナムは抗緑膿菌セファロスポリン系薬と同じような抗緑膿菌活性を発揮するが、あまり選択されない。その主な理由は、グラム陽性菌および嫌気性菌といった緑膿菌と同時に分離されることの多い細菌に対する活性が低いからである。抗緑膿菌薬と考えられているキノロン系薬は二種類ある。シプロフロキサシンとレボフロキサシンである(Table 1)。シプロフロキサシンのMIC(0.5mcg/mL)はレボフロキサシンのMIC(1.0mcg/mL)より低く、シプロフロキサシンの方がやや強力なように思われるものの、血中および組織移行性がレボフロキサシンより低いため、この程度の差は帳消しになってしまう。つまり、この二剤の抗緑膿菌活性はほぼ同等ということになる。
耐性の疫学
緑膿菌の抗菌薬耐性はどんどん進化している(Table 2)。米国で行われた三件の大規模調査で過去9~13年のあいだに、フルオロキノロン耐性(15%→40%)、第三世代セファロスポリン耐性(15%→32%)およびカルバペネム耐性(13%→23%)を示す緑膿菌が増えていることが明らかになっている。分離される緑膿菌は、57%~67%が気道検体のものである。
ICUに収容されている気管挿管患者では、抗緑膿菌抗菌薬の投与開始から10日以内に多剤耐性緑膿菌が検出されることがある。交叉耐性が見られることも珍しくない。例えば、ピペラシリン耐性緑膿菌およびシプロフロキサシン耐性緑膿菌は、それぞれピペラシリン感受性緑膿菌およびシプロフロキサシン緑膿菌と比べ、他の系統の緑膿菌にも耐性を示す頻度が高いことが分かっている。
抗菌薬耐性
緑膿菌は、院内肺炎の原因となる多剤耐性グラム陰性桿菌の代表格である。緑膿菌の抗菌薬耐性(自然耐性)発現には少なくとも5通りの機構が関与している。さらに、抗菌薬耐性(獲得耐性)をエンコードする遺伝子を獲得することもできる。主要な耐性化機構は以下の三つである:βラクタマーゼの産生、外膜タンパクの欠損および薬剤排出ポンプのアップレギュレーション(Table 2)。ジャイレースの変異および酵素の不活化は、それぞれキノロン系薬およびアミノグリコシド系薬に特異的な耐性化機構である。以上の耐性化機構は、一つの細菌に同時に複数が存在することがある。これが多剤耐性化の正体である。
緑膿菌は色々な種類のβラクタマーゼを作りだし、広く拡散したり、思いがけない耐性パターンが出現したりすることになる。緑膿菌が産生するβラクタマーゼのうち、AmpC遺伝子が産生するものが大部分を占める。このβラクタマーゼには、様々な抗緑膿菌抗菌薬によって「誘導される」という特性があるため、耐性化に拍車がかかる。AmpC βラクタマーゼは菌体内からの調節によって抑制される。ある種の抗菌薬に曝露されて変異した緑膿菌は、大量のAmpC βラクタマーゼを産生するようになる。このような「脱抑制」化した変異株には、第三世代セファロスポリン系薬およびチカルシリン/クラブラン酸が選択される。基質特異性拡張型βラクタマーゼ(ESBL; extended-spectrum β-lactamase)は、第三世代セファロスポリン系薬、抗緑膿菌ペニシリン系薬および第一世代、第二世代セファロスポリン系薬を加水分解する働きを持つ(Table 1)。ESBL獲得には、配列挿入、トランスポゾンおよびインテグロンなどの遺伝的機構が関わっている。
教訓 緑膿菌が産生するβラクタマーゼには、様々な抗緑膿菌抗菌薬によって「誘導される」という性質があります。ESBLは第三世代セファロスポリン系薬、抗緑膿菌ペニシリン系薬および第一世代、第二世代セファロスポリン系薬を加水分解します。
2011-07-19 08:21
コメント(0)
緑膿菌肺炎~水まわりに注意 [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part I: Epidemiology, Clinical Diagnosis, and Source
CHEST 2011年4月号より
緑膿菌の巣
定着
気道への緑膿菌の定着は、院内肺炎発症の前駆現象である。ICUでは、緑膿菌の定着と在室期間、人工呼吸期間および抗菌薬使用歴とのあいだに有意な相関があることが分かっている。すでに咽喉頭または消化管に緑膿菌が定着している患者の入院が、入院中の患者における緑膿菌の定着の原因となり得る。生の果物や野菜が緑膿菌による院内感染の原因であったとする報告もあるが、この広く人口に膾炙している憶測を裏付ける検証結果は示されていない。
水道水は緑膿菌の巣
緑膿菌感染症の集団発生例のうち交叉感染を原因とする例も二、三あるが、環境からの感染が原因である場合の方がずっと多い。意外にも、病院環境を原因とする緑膿菌は、他の患者から交叉感染する緑膿菌と異なり、抗緑膿菌抗菌薬に対する耐性が高い。また、入院前からの緑膿菌定着のある患者の緑膿菌が他の患者に定着・感染するよりも、病院環境に棲息する緑膿菌は定着、感染しやすい性質を持っている。緑膿菌に汚染された水道水を手術や医療機器の洗浄に用いると、緑膿菌による菌血症や腹腔内感染などの院内感染を起こすことがある。気管支鏡に関連する呼吸器感染症について本レビューの別項で既に触れたが、その一部は気管支鏡洗浄に用いた水道水が元凶である可能性がある。
病院によっては水道水が緑膿菌をばらまく主犯であるかもしれない。ICUにおける緑膿菌集団感染(6編)もしくは緑膿菌感染/定着(12編)について3ヶ月から3年にわたって発生源を調査した計18編の研究がある。対象患者は3名から7269名である。全18編のうち14編で、水道水、蛇口またはシンクが緑膿菌発生源として考え得るとの結論が示されている。患者間または患者-医療従事者間の交叉感染を原因として挙げているのが8編、患者自身がもともと持っている細菌叢に原因があるという結果を示した研究は2編であった。緑膿菌は物体表面では数ヶ月、医療従事者の手では3時間生存する。このことが緑膿菌の伝播を可能にしている一因である。
水道水、蛇口またはシンクが緑膿菌発生源であり得ることを示した前述の14編の研究では、水道水/蛇口/シンク検体の9.1%~97%において緑膿菌が分離されたことが報告されている。分子サブタイプ解析を行ったところ、患者から分離された緑膿菌が、水道水/蛇口/シンクから分離された緑膿菌と一致した割合は19.2%~100%であった。病院の水道水に起因する緑膿菌定着が発生しうる一方で、患者のもともと保有している緑膿菌が病院の水供給経路のどこかを汚染している可能性もある。緑膿菌が分離された患者のうち40%~46.7%が、水道水からの感染であることが2編の研究で示されているが、同時に、蛇口検体の11%~52.4%は患者によって汚染された可能性も浮かび上がった。
患者から検出された緑膿菌のうち29.5%~52.6%は交叉感染によるものであるとされている。これは、他の患者で検出された緑膿菌と分子サブタイプが一致することで確認を行った研究の結果である。医療従事者の3%~6%において手から緑膿菌が分離される。そのうち10%~20%は患者から分離される緑膿菌と遺伝子型が同一である。
感染制御策が7編の研究で示されている。特定の医療従事者一名が感染源であった例についての一編の論文では、その医療従事者を患者とは直接関わらない部署に異動させるとともに、その他の感染予防策を実施したところ集団感染が終熄したと報告されている。残りの6編では水道水、蛇口またはシンクが感染源であった。そのうち3編では蛇口出口部分、シンク、シャワーヘッド、シャワーホースなどを交換または定期交換した。二編では水温を上昇させ、銅および銀イオン消毒または塩素消毒を実施した。三編では浄水フィルタを設置した。二編では感染予防策を強化徹底した。多剤耐性緑膿菌単独株に36名が感染した集団発生例では、手洗いに用いていたシンクが元凶であることが判明した。そのシンクは、処置や薬の準備をしたりするのに使用する台に隣接しており、病床にも近接していた。水しぶきが飛び散らないようにする遮蔽板を設置したところ、集団発生は終熄した。
浄水フィルタの導入は、最も注目すべき対策である。これは、緑膿菌の増殖を抑えるだけでなく、緑膿菌定着を85%も減らし、さらには肺炎や菌血症などの感染をも減少させる効果を発揮する。蛇口の消毒とシャワーヘッドおよびシャワーホースの交換は無効であることが示されていて、医療関連レジオネラ感染についても同様の知見が得られている。高温水および銅/銀イオン消毒によって、緑膿菌定着例および感染例の年間発生数は低下するが、緑膿菌がバイオフィルムを形成して蛇口へ定着することを防ぐことはできない。Anaissieらは飲用、歯磨きおよび胃管の洗浄には滅菌水の使用を推奨している。緑膿菌と密接な関係のある疾患の悪性(壊死性)外耳炎は、水道水の緑膿菌からの感染例が大部分を占める。
まとめ
緑膿菌肺炎は、臨床的には数種類の異なるタイプに分類される。最も一般的なのは、ICUで発症する院内肺炎としての緑膿菌肺炎である。緑膿菌による院内肺炎の死亡率や金銭的負担は、いまもって容認できないほど高い。緑膿菌による市中肺炎は稀であり、発生例は慢性肺疾患患者に概ね限られる。院内肺炎と同様に死亡率が高い。HIV陽性患者における菌血症からの肺炎発症は、わりと最近になって登場した話題である。免疫抑制患者(特に好中球減少症の患者)の細菌性肺炎は減っている。これはおそらく、癌化学療法が進化したおかげである。
緑膿菌肺炎の診断は一筋縄ではいかない。なぜなら、気道から緑膿菌が分離されても、感染ではなく定着に過ぎないことが多いからである。COPD患者や、入院期間が長期化している患者では、とりわけその傾向が認められる。したがって、気道から得た検体の培養結果を根拠に抗緑膿菌抗菌薬を投与すると、不要な治療をわざわざ行っていることになりかねない。侵襲的検査による定量培養が、抗菌薬療法の本当のターゲットになる患者を選別するのに有効であることが明らかにされている。その代わりの選択肢となるのが、CPISを用いて予測的治療の方針を決定する侵襲のすくない方法である。この方法によって、適応がないのに抗菌薬を投与してしまうのを防ぐことができる。水道水が緑膿菌の感染源となっているICUもあるため、水供給システムを対象とした予防策を講ずることによって定着、そして感染の発生頻度を減らすことができる可能性がある。
教訓 病院環境に棲息している緑膿菌は、患者間で交叉感染する緑膿菌より抗緑膿菌抗菌薬に対する耐性が高く、定着・感染力も強いことが分かっています。水道水、蛇口またはシンクには緑膿菌が住みつきやすいので、注意しなければなりません。
CHEST 2011年4月号より
緑膿菌の巣
定着
気道への緑膿菌の定着は、院内肺炎発症の前駆現象である。ICUでは、緑膿菌の定着と在室期間、人工呼吸期間および抗菌薬使用歴とのあいだに有意な相関があることが分かっている。すでに咽喉頭または消化管に緑膿菌が定着している患者の入院が、入院中の患者における緑膿菌の定着の原因となり得る。生の果物や野菜が緑膿菌による院内感染の原因であったとする報告もあるが、この広く人口に膾炙している憶測を裏付ける検証結果は示されていない。
水道水は緑膿菌の巣
緑膿菌感染症の集団発生例のうち交叉感染を原因とする例も二、三あるが、環境からの感染が原因である場合の方がずっと多い。意外にも、病院環境を原因とする緑膿菌は、他の患者から交叉感染する緑膿菌と異なり、抗緑膿菌抗菌薬に対する耐性が高い。また、入院前からの緑膿菌定着のある患者の緑膿菌が他の患者に定着・感染するよりも、病院環境に棲息する緑膿菌は定着、感染しやすい性質を持っている。緑膿菌に汚染された水道水を手術や医療機器の洗浄に用いると、緑膿菌による菌血症や腹腔内感染などの院内感染を起こすことがある。気管支鏡に関連する呼吸器感染症について本レビューの別項で既に触れたが、その一部は気管支鏡洗浄に用いた水道水が元凶である可能性がある。
病院によっては水道水が緑膿菌をばらまく主犯であるかもしれない。ICUにおける緑膿菌集団感染(6編)もしくは緑膿菌感染/定着(12編)について3ヶ月から3年にわたって発生源を調査した計18編の研究がある。対象患者は3名から7269名である。全18編のうち14編で、水道水、蛇口またはシンクが緑膿菌発生源として考え得るとの結論が示されている。患者間または患者-医療従事者間の交叉感染を原因として挙げているのが8編、患者自身がもともと持っている細菌叢に原因があるという結果を示した研究は2編であった。緑膿菌は物体表面では数ヶ月、医療従事者の手では3時間生存する。このことが緑膿菌の伝播を可能にしている一因である。
水道水、蛇口またはシンクが緑膿菌発生源であり得ることを示した前述の14編の研究では、水道水/蛇口/シンク検体の9.1%~97%において緑膿菌が分離されたことが報告されている。分子サブタイプ解析を行ったところ、患者から分離された緑膿菌が、水道水/蛇口/シンクから分離された緑膿菌と一致した割合は19.2%~100%であった。病院の水道水に起因する緑膿菌定着が発生しうる一方で、患者のもともと保有している緑膿菌が病院の水供給経路のどこかを汚染している可能性もある。緑膿菌が分離された患者のうち40%~46.7%が、水道水からの感染であることが2編の研究で示されているが、同時に、蛇口検体の11%~52.4%は患者によって汚染された可能性も浮かび上がった。
患者から検出された緑膿菌のうち29.5%~52.6%は交叉感染によるものであるとされている。これは、他の患者で検出された緑膿菌と分子サブタイプが一致することで確認を行った研究の結果である。医療従事者の3%~6%において手から緑膿菌が分離される。そのうち10%~20%は患者から分離される緑膿菌と遺伝子型が同一である。
感染制御策が7編の研究で示されている。特定の医療従事者一名が感染源であった例についての一編の論文では、その医療従事者を患者とは直接関わらない部署に異動させるとともに、その他の感染予防策を実施したところ集団感染が終熄したと報告されている。残りの6編では水道水、蛇口またはシンクが感染源であった。そのうち3編では蛇口出口部分、シンク、シャワーヘッド、シャワーホースなどを交換または定期交換した。二編では水温を上昇させ、銅および銀イオン消毒または塩素消毒を実施した。三編では浄水フィルタを設置した。二編では感染予防策を強化徹底した。多剤耐性緑膿菌単独株に36名が感染した集団発生例では、手洗いに用いていたシンクが元凶であることが判明した。そのシンクは、処置や薬の準備をしたりするのに使用する台に隣接しており、病床にも近接していた。水しぶきが飛び散らないようにする遮蔽板を設置したところ、集団発生は終熄した。
浄水フィルタの導入は、最も注目すべき対策である。これは、緑膿菌の増殖を抑えるだけでなく、緑膿菌定着を85%も減らし、さらには肺炎や菌血症などの感染をも減少させる効果を発揮する。蛇口の消毒とシャワーヘッドおよびシャワーホースの交換は無効であることが示されていて、医療関連レジオネラ感染についても同様の知見が得られている。高温水および銅/銀イオン消毒によって、緑膿菌定着例および感染例の年間発生数は低下するが、緑膿菌がバイオフィルムを形成して蛇口へ定着することを防ぐことはできない。Anaissieらは飲用、歯磨きおよび胃管の洗浄には滅菌水の使用を推奨している。緑膿菌と密接な関係のある疾患の悪性(壊死性)外耳炎は、水道水の緑膿菌からの感染例が大部分を占める。
まとめ
緑膿菌肺炎は、臨床的には数種類の異なるタイプに分類される。最も一般的なのは、ICUで発症する院内肺炎としての緑膿菌肺炎である。緑膿菌による院内肺炎の死亡率や金銭的負担は、いまもって容認できないほど高い。緑膿菌による市中肺炎は稀であり、発生例は慢性肺疾患患者に概ね限られる。院内肺炎と同様に死亡率が高い。HIV陽性患者における菌血症からの肺炎発症は、わりと最近になって登場した話題である。免疫抑制患者(特に好中球減少症の患者)の細菌性肺炎は減っている。これはおそらく、癌化学療法が進化したおかげである。
緑膿菌肺炎の診断は一筋縄ではいかない。なぜなら、気道から緑膿菌が分離されても、感染ではなく定着に過ぎないことが多いからである。COPD患者や、入院期間が長期化している患者では、とりわけその傾向が認められる。したがって、気道から得た検体の培養結果を根拠に抗緑膿菌抗菌薬を投与すると、不要な治療をわざわざ行っていることになりかねない。侵襲的検査による定量培養が、抗菌薬療法の本当のターゲットになる患者を選別するのに有効であることが明らかにされている。その代わりの選択肢となるのが、CPISを用いて予測的治療の方針を決定する侵襲のすくない方法である。この方法によって、適応がないのに抗菌薬を投与してしまうのを防ぐことができる。水道水が緑膿菌の感染源となっているICUもあるため、水供給システムを対象とした予防策を講ずることによって定着、そして感染の発生頻度を減らすことができる可能性がある。
教訓 病院環境に棲息している緑膿菌は、患者間で交叉感染する緑膿菌より抗緑膿菌抗菌薬に対する耐性が高く、定着・感染力も強いことが分かっています。水道水、蛇口またはシンクには緑膿菌が住みつきやすいので、注意しなければなりません。
2011-07-15 07:18
コメント(0)
緑膿菌肺炎~診断② [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part I: Epidemiology, Clinical Diagnosis, and Source
CHEST 2011年4月号より
診断手順
侵襲的検査による定量培養が望ましいと言われている。明確な診断手順を確立しようと多くの研究が行われてきたが、すでに抗菌薬を使用している場合をどう扱うかとか、検査手順が標準化されていなかったり、結果を判定する診断基準が統一されていなかったり、といった色々な問題点がつきまとっていて、決定版と言えるような診断手順はまだない。三種類の診断手順が無作為化試験で評価されおり、この三つは肺炎が疑われる患者において実用に耐える方法であると考えられる。
1. フランスに所在する31か所のICUにおいて413名の患者を対象に見事な比較対照試験が行われ、侵襲的検査によってVAPの診断を行うと、広域スペクトラム抗菌薬の使用量が減り、死亡率が向上することが明らかにされている。この研究ではPSB(protected specimen brush)を用いた気管支鏡検査で検体を得て、定量培養の結果について、定着は細菌数10^3cfu/mL未満、感染は細菌数10^3cfu/mL以上という診断基準を設けた。緑膿菌(またはアシネトバクター属)に感染していた患者は、これらの細菌の定着患者よりも死亡率が有意に高かった。
2. 気管内吸引で得られた検体の定量培養は今すぐにでも実施可能な方法である。この方法をBAL検体の定量培養と比較する多施設無作為化試験が、北米に所在する28か所のICUに収容された患者740名を対象として実施された。両群の転帰と抗菌薬総使用量は同等であった。この研究には、緑膿菌が分離された患者を除外したという重大な注意点がある。
3. 肺に浸潤影のある患者において、抗菌薬一剤を三日間使用するだけにとどめる予測的抗菌薬投与の可否をCPISの点数をもとに判断できるかどうかが検証された。この方法では、肺炎を本当に発症しているのかそうでないのかの判断はしないのだが、CPISの点数が低ければ、感染の可能性は低く、患者の状態は安定していると考えられる。この方法は患者管理の実態に即していて、予測的に広域スペクトラム抗菌薬を長期間投与する現行の方法に取って代わる安全な選択肢である。肺炎と定着を見分けるのは往々にして困難であるため、このような方法を実施すれば、耐性緑膿菌による重複感染や抗菌薬の副作用などのリスクに患者を曝すことなく、治療効果を最大限に引き出すことが可能である。三日後に培養結果を見て再評価を行えば、抗菌薬を安心して止めることができる。
画像所見
(略)
緑膿菌肺炎に特異的な画像所見はない。緑膿菌肺炎の確定診断に胸部X線写真を用いることはできない。
教訓 緑膿菌肺炎の確定診断には、気管支鏡を用いて得た検体(PSB、BAL、気管内採痰)の定量培養が必要です。その上で、細菌量や臨床所見から定着か感染かを見極めなければなりません。
CHEST 2011年4月号より
診断手順
侵襲的検査による定量培養が望ましいと言われている。明確な診断手順を確立しようと多くの研究が行われてきたが、すでに抗菌薬を使用している場合をどう扱うかとか、検査手順が標準化されていなかったり、結果を判定する診断基準が統一されていなかったり、といった色々な問題点がつきまとっていて、決定版と言えるような診断手順はまだない。三種類の診断手順が無作為化試験で評価されおり、この三つは肺炎が疑われる患者において実用に耐える方法であると考えられる。
1. フランスに所在する31か所のICUにおいて413名の患者を対象に見事な比較対照試験が行われ、侵襲的検査によってVAPの診断を行うと、広域スペクトラム抗菌薬の使用量が減り、死亡率が向上することが明らかにされている。この研究ではPSB(protected specimen brush)を用いた気管支鏡検査で検体を得て、定量培養の結果について、定着は細菌数10^3cfu/mL未満、感染は細菌数10^3cfu/mL以上という診断基準を設けた。緑膿菌(またはアシネトバクター属)に感染していた患者は、これらの細菌の定着患者よりも死亡率が有意に高かった。
2. 気管内吸引で得られた検体の定量培養は今すぐにでも実施可能な方法である。この方法をBAL検体の定量培養と比較する多施設無作為化試験が、北米に所在する28か所のICUに収容された患者740名を対象として実施された。両群の転帰と抗菌薬総使用量は同等であった。この研究には、緑膿菌が分離された患者を除外したという重大な注意点がある。
3. 肺に浸潤影のある患者において、抗菌薬一剤を三日間使用するだけにとどめる予測的抗菌薬投与の可否をCPISの点数をもとに判断できるかどうかが検証された。この方法では、肺炎を本当に発症しているのかそうでないのかの判断はしないのだが、CPISの点数が低ければ、感染の可能性は低く、患者の状態は安定していると考えられる。この方法は患者管理の実態に即していて、予測的に広域スペクトラム抗菌薬を長期間投与する現行の方法に取って代わる安全な選択肢である。肺炎と定着を見分けるのは往々にして困難であるため、このような方法を実施すれば、耐性緑膿菌による重複感染や抗菌薬の副作用などのリスクに患者を曝すことなく、治療効果を最大限に引き出すことが可能である。三日後に培養結果を見て再評価を行えば、抗菌薬を安心して止めることができる。
画像所見
(略)
緑膿菌肺炎に特異的な画像所見はない。緑膿菌肺炎の確定診断に胸部X線写真を用いることはできない。
教訓 緑膿菌肺炎の確定診断には、気管支鏡を用いて得た検体(PSB、BAL、気管内採痰)の定量培養が必要です。その上で、細菌量や臨床所見から定着か感染かを見極めなければなりません。
2011-07-14 07:40
コメント(0)
緑膿菌肺炎~診断① [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part I: Epidemiology, Clinical Diagnosis, and Source
CHEST 2011年4月号より
診断
緑膿菌は上気道や下気道に比較的容易に定着するため、緑膿菌肺炎の診断には困難がつきまとう。好中球減少症患者や重症免疫抑制患者における緑膿菌肺炎を除いては、緑膿菌による院内肺炎で血液培養が陽性になることは滅多にない。気管挿管患者では、全身感染の徴候がないのに長期にわたって気管内採痰から緑膿菌が常に分離されることがある。気管気管支炎を発症している場合は膿性の喀痰または気管内採痰の培養結果は当てにならないと考えられるが、気管気管支炎が肺炎へと進展する場合もある。現実的な対応を重んずる臨床医の大方の意見では、気道分泌物の量が突然増えたり、性状が急に膿性に変化したりした場合は、抗菌薬開始を考慮すべきである。人工呼吸器関連肺炎(VAP)の患者では、気管支肺胞洗浄液を遠心分離して細胞内に微生物が存在することが分かった場合、それは感染であることを示す特異的な所見である。この所見の感度は37%~100%である。
定着か感染か
COPD患者の4%~15%では、肺炎を発症していなくても痰から緑膿菌が分離される。過去の抗菌薬使用歴は緑膿菌定着の危険因子である。広域スペクトラム抗菌薬の使用は、ICUにおける緑膿菌定着の増加につながり、気管内採痰中の主な定着菌が緑膿菌となることが分かっている。緑膿菌は粘液分泌を増やし、繊毛運動を妨害し、気道上皮傷害を引き起こす。その結果、肺の分泌物浄化能が低下する。気道から分離される緑膿菌は、ICU患者の血中から分類される緑膿菌と比べ、耐性菌であることが多く、毒素産生能が低く、バイオフィルム形成能は高い傾向がある。VAP発症から8日経過し、感受性のある抗菌薬を投与していても、まだ緑膿菌が分離されることもある。緑膿菌によるVAPを繰り返す場合の多くが、前回の緑膿菌感染が治りきっていないケースであることが、分子サブタイプ解析で判明している。
緑膿菌による院内肺炎では菌血症が見られることは非常に稀であるため、緑膿菌が起因菌であるのかそうでないのかの確定診断を下すのは困難である。したがって、肺の浸潤影が新たに出現し肺炎の臨床徴候を呈する患者の気道分泌物から緑膿菌が分離されれば、それは緑膿菌肺炎であることの状況証拠となり、抗緑膿菌抗菌薬の投与を開始する根拠となる。
医療関連肺炎患者を対象とした前向き二重盲検抗菌薬比較試験では、二名の痰培から緑膿菌が分離されエルタペネムが予測的に投与された。in vitro検査ではエルタペネムの抗緑膿菌活性は十分ではなかったが、二例とも治療が奏功した。我々は、CPIS(Clinical Pulmonary Infection Score)が7点未満で、長期の多剤併用療法の適応とはならなかった二例を経験した。二例のうち一例はCOPD患者であった。第3日に気道分泌物から緑膿菌が多量に検出されたが、CPISはまだ低いままであった。CPISプロトコルに従い、キノロン系薬の予測的投与を開始した。二例とも、分離された緑膿菌はin vitroでキノロン耐性であった。CPISが低かったので、プロトコル通りに投与3日目にキノロン系薬を中止した。それ以降、抗緑膿菌薬を投与しなかったが、二例とも肺の浸潤影は徐々に改善した。その後、何週間にもわたって気道から緑膿菌が検出されたが、二名とも状態は安定していた。このエピソードは、緑膿菌が検出されても定着であることが多く、肺の浸潤影は必ずしも感染を意味しないということを裏付けている。そして、ICU患者を対象とした研究で緑膿菌肺炎の発生頻度が高いのは、定着が交絡因子になっていることが明白であり、データの信憑性に関して疑問がもたげてくる。
高次医療施設のICUで行われた研究で、気管挿管中の患者において気管内採痰の監視培養が毎日行われた。定量培養で、45名において多数の緑膿菌が認められた。このうち、VAPの臨床診断基準を満たさなかった患者が17名(37.8%)存在した。すなわち、この17名においては、緑膿菌が検出された培養検体採取日には新規または増悪する浸潤影が胸部X線写真上で認められなかったのである。だが、この17名の死亡率は高かった(VAPの診断基準を満たし、培養で緑膿菌が分離された患者よりも死亡率が高かった)。さらに、長期(月単位)にわたり機械的人工呼吸管理を受けていて状態が安定している患者では、肺炎でなくても肺胞内に多量の最近が定着していることがあることが明らかにされている。CPISが6点以下で肺に浸潤影のあるICU患者において抗菌薬の使用を控えても、死亡率は上昇せず、かえって低下する。肺に浸潤影があり緑膿菌が分離されるICU患者は多いが、これは単にICU在室日数の長期化や、死亡率上昇の指標であるに過ぎず、本当に緑膿菌が病原菌として肺に存在し、強力な抗菌薬投与を要することを意味するわけではないものと考えられる。
教訓 痰から緑膿菌が検出されたときは、定着か感染かを見極める必要があります。COPD患者の4%~15%では、肺炎を発症していなくても痰から緑膿菌が分離されます。過去の抗菌薬使用歴は緑膿菌定着の危険因子です。広域スペクトラム抗菌薬の使用は、ICUにおける緑膿菌定着の増加につながります。
CHEST 2011年4月号より
診断
緑膿菌は上気道や下気道に比較的容易に定着するため、緑膿菌肺炎の診断には困難がつきまとう。好中球減少症患者や重症免疫抑制患者における緑膿菌肺炎を除いては、緑膿菌による院内肺炎で血液培養が陽性になることは滅多にない。気管挿管患者では、全身感染の徴候がないのに長期にわたって気管内採痰から緑膿菌が常に分離されることがある。気管気管支炎を発症している場合は膿性の喀痰または気管内採痰の培養結果は当てにならないと考えられるが、気管気管支炎が肺炎へと進展する場合もある。現実的な対応を重んずる臨床医の大方の意見では、気道分泌物の量が突然増えたり、性状が急に膿性に変化したりした場合は、抗菌薬開始を考慮すべきである。人工呼吸器関連肺炎(VAP)の患者では、気管支肺胞洗浄液を遠心分離して細胞内に微生物が存在することが分かった場合、それは感染であることを示す特異的な所見である。この所見の感度は37%~100%である。
定着か感染か
COPD患者の4%~15%では、肺炎を発症していなくても痰から緑膿菌が分離される。過去の抗菌薬使用歴は緑膿菌定着の危険因子である。広域スペクトラム抗菌薬の使用は、ICUにおける緑膿菌定着の増加につながり、気管内採痰中の主な定着菌が緑膿菌となることが分かっている。緑膿菌は粘液分泌を増やし、繊毛運動を妨害し、気道上皮傷害を引き起こす。その結果、肺の分泌物浄化能が低下する。気道から分離される緑膿菌は、ICU患者の血中から分類される緑膿菌と比べ、耐性菌であることが多く、毒素産生能が低く、バイオフィルム形成能は高い傾向がある。VAP発症から8日経過し、感受性のある抗菌薬を投与していても、まだ緑膿菌が分離されることもある。緑膿菌によるVAPを繰り返す場合の多くが、前回の緑膿菌感染が治りきっていないケースであることが、分子サブタイプ解析で判明している。
緑膿菌による院内肺炎では菌血症が見られることは非常に稀であるため、緑膿菌が起因菌であるのかそうでないのかの確定診断を下すのは困難である。したがって、肺の浸潤影が新たに出現し肺炎の臨床徴候を呈する患者の気道分泌物から緑膿菌が分離されれば、それは緑膿菌肺炎であることの状況証拠となり、抗緑膿菌抗菌薬の投与を開始する根拠となる。
医療関連肺炎患者を対象とした前向き二重盲検抗菌薬比較試験では、二名の痰培から緑膿菌が分離されエルタペネムが予測的に投与された。in vitro検査ではエルタペネムの抗緑膿菌活性は十分ではなかったが、二例とも治療が奏功した。我々は、CPIS(Clinical Pulmonary Infection Score)が7点未満で、長期の多剤併用療法の適応とはならなかった二例を経験した。二例のうち一例はCOPD患者であった。第3日に気道分泌物から緑膿菌が多量に検出されたが、CPISはまだ低いままであった。CPISプロトコルに従い、キノロン系薬の予測的投与を開始した。二例とも、分離された緑膿菌はin vitroでキノロン耐性であった。CPISが低かったので、プロトコル通りに投与3日目にキノロン系薬を中止した。それ以降、抗緑膿菌薬を投与しなかったが、二例とも肺の浸潤影は徐々に改善した。その後、何週間にもわたって気道から緑膿菌が検出されたが、二名とも状態は安定していた。このエピソードは、緑膿菌が検出されても定着であることが多く、肺の浸潤影は必ずしも感染を意味しないということを裏付けている。そして、ICU患者を対象とした研究で緑膿菌肺炎の発生頻度が高いのは、定着が交絡因子になっていることが明白であり、データの信憑性に関して疑問がもたげてくる。
高次医療施設のICUで行われた研究で、気管挿管中の患者において気管内採痰の監視培養が毎日行われた。定量培養で、45名において多数の緑膿菌が認められた。このうち、VAPの臨床診断基準を満たさなかった患者が17名(37.8%)存在した。すなわち、この17名においては、緑膿菌が検出された培養検体採取日には新規または増悪する浸潤影が胸部X線写真上で認められなかったのである。だが、この17名の死亡率は高かった(VAPの診断基準を満たし、培養で緑膿菌が分離された患者よりも死亡率が高かった)。さらに、長期(月単位)にわたり機械的人工呼吸管理を受けていて状態が安定している患者では、肺炎でなくても肺胞内に多量の最近が定着していることがあることが明らかにされている。CPISが6点以下で肺に浸潤影のあるICU患者において抗菌薬の使用を控えても、死亡率は上昇せず、かえって低下する。肺に浸潤影があり緑膿菌が分離されるICU患者は多いが、これは単にICU在室日数の長期化や、死亡率上昇の指標であるに過ぎず、本当に緑膿菌が病原菌として肺に存在し、強力な抗菌薬投与を要することを意味するわけではないものと考えられる。
教訓 痰から緑膿菌が検出されたときは、定着か感染かを見極める必要があります。COPD患者の4%~15%では、肺炎を発症していなくても痰から緑膿菌が分離されます。過去の抗菌薬使用歴は緑膿菌定着の危険因子です。広域スペクトラム抗菌薬の使用は、ICUにおける緑膿菌定着の増加につながります。
2011-07-13 07:29
コメント(0)
緑膿菌肺炎~疫学② [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part I: Epidemiology, Clinical Diagnosis, and Source
CHEST 2011年4月号より
市中肺炎(CAP)
緑膿菌は市中肺炎の起因菌としては稀であることが観測研究で明らかにされている。市中肺炎入院例のうち起因菌が緑膿菌の例は0.9%から1.9%を占める。市中肺炎患者計33148名を対象にした研究127編についてのメタ分析では、緑膿菌感染はわずか18例で、その粗死亡率は61.1%であった(11/18)。2000年に発表された総説では、元来健康な成人患者の緑膿菌市中肺炎の報告例が検討された。血液、肺組織または胸水から緑膿菌が分離され感染が確認された症例という厳しい基準を用いて、世界各国からの発表された論文を渉猟した結果、わずか12例しか報告例がないことが分かった。
一方、ICUで行われた市中肺炎の調査では、緑膿菌も起因菌の一つには挙げられているが頻度は低いことが報告されている。重症市中肺炎、すなわちICU入室を要するかもしくはショックに陥るほどの市中肺炎の場合、緑膿菌による者が1.8%~8.3%を占め、死亡率は50%~100%にのぼる。とあるICU一施設からの報告では、起因菌が判明した市中肺炎のうち、緑膿菌によるものが三番目に多いという結果が得られている(一般的には、一番多いのが肺炎球菌、二番はレジオネラである)。以上に紹介したICUにおける調査には、起因菌を緑膿菌をと判定する方法に問題があり、細菌学検査で確定診断が得られた症例は44.4%~78.6%を占めるに過ぎない。
過去に行われた研究では、前回入院から今回の入院までの期間や、患者が医療関連肺炎の診断基準を満たすかどうかについては、きちんと記されていない。医療関連肺炎とは、前回入院から30日以内もしくは一年以内に発症した肺炎を指す。30日以内の発症例を医療関連肺炎と定義した研究では市中肺炎の17.1%、一年以内と定義した別の研究では4.8%が緑膿菌によるものであった。そして、医療関連肺炎のそれぞれ25.3%、25.5%が緑膿菌を起因菌とする肺炎であった。翻って、ドイツ市中肺炎ネットワークが行った5130名を対象とした前向き研究では、厳格な基準を設けて判定したところ、緑膿菌が起因菌であると同定されたのは22名であった。一名は血液から緑膿菌が分離され、残りの21名はグラム染色で診断された例である。発生頻度は0.4%(22/5130)ということになる。この22名の死亡率は18%であった。スペインで行われた市中肺炎患者780名についての前向き研究でも、緑膿菌が起因菌であった症例は少ないことが分かっている。
緑膿菌による市中肺炎の危険因子については、多くの知見が得られている。肺疾患、特にCOPDはいずれの研究においても危険因子であることが明らかにされている。その他の危険因子は、過去の入院歴、気管挿管および経腸栄養であり、いずれの場合も緑膿菌の定着が感染発症に先行することが分かっている。これらの危険因子を持つ場合は、正確には医療関連肺炎と分類すべきであろう。COPD and/or喫煙、HIV感染もしくは肺の構造に異常が生ずる疾患(気管支拡張症など)がある患者では、市中肺炎の起因菌が緑膿菌であることは珍しくない。
HIV陽性患者における緑膿菌肺炎
高活性抗レトロウイルス療法(HAART; highly active anti-retroviral therapy)が登場する以前は、HIV陽性成人ではHIV陰性成人と比べ、細菌性肺炎発生頻度が有意に高く(5.5 vs 0.9/100人年、P<0.01)、CD4リンパ球数が減るほど肺炎発生頻度が増えるとされていた。HARRT前の時代には、肺炎球菌が起因菌として最多であり(25%~46.7%)、緑膿菌は8%~25%を占めていた。院内肺炎の起因菌の中では緑膿菌が最多であった(21.4%~38.7%)。緑膿菌肺炎による死亡率は42%~55%で、他の起因菌による肺炎の死亡率よりも極めて高い。緑膿菌による市中肺炎を発症したHIV陽性患者16名の平均CD4リンパ球数は、わずか27/μLで、69%の患者において空洞性病変が胸部X線写真で認められた。好中球減少、最近の入院歴または抗菌薬使用歴といった典型的な危険因子を有する症例はなかった。ニューモシスティス肺炎の予防に使用するST合剤は、トキソプラズマ、サルモネラ、ヘモフィルス、黄色ブドウ球菌に対しても有効であるが、肺炎球菌、肺炎球菌以外の連鎖球菌および緑膿菌には無効である。
HAARTの登場によって、HIV感染症が進行した患者の合併症発生率および死亡率は劇的に低下した。しかし、HIV患者における細菌性肺炎の発生頻度は必ずしも低下しておらず、入院理由として最も多いのは依然として細菌性肺炎である。HAART時代の現在でも、市中肺炎の起因菌として最も多いのは肺炎球菌であり、緑膿菌は5%~6.7%を占める。緑膿菌がHIV患者における院内肺炎の起因菌として最多であるのは今も変わらず、緑膿菌院内肺炎の死亡率は23%である。緑膿菌肺炎患者のCD4リンパ球数は入院時の平均値は27~42/μLで、HAART前の時代と同等である。
教訓 緑膿菌による市中肺炎はまれです。ただし、COPD 、喫煙、HIV感染もしくは肺の構造に異常が生ずる疾患(気管支拡張症など)といった因子を持つ患者では、緑膿菌による市中肺炎は珍しくありません。
CHEST 2011年4月号より
市中肺炎(CAP)
緑膿菌は市中肺炎の起因菌としては稀であることが観測研究で明らかにされている。市中肺炎入院例のうち起因菌が緑膿菌の例は0.9%から1.9%を占める。市中肺炎患者計33148名を対象にした研究127編についてのメタ分析では、緑膿菌感染はわずか18例で、その粗死亡率は61.1%であった(11/18)。2000年に発表された総説では、元来健康な成人患者の緑膿菌市中肺炎の報告例が検討された。血液、肺組織または胸水から緑膿菌が分離され感染が確認された症例という厳しい基準を用いて、世界各国からの発表された論文を渉猟した結果、わずか12例しか報告例がないことが分かった。
一方、ICUで行われた市中肺炎の調査では、緑膿菌も起因菌の一つには挙げられているが頻度は低いことが報告されている。重症市中肺炎、すなわちICU入室を要するかもしくはショックに陥るほどの市中肺炎の場合、緑膿菌による者が1.8%~8.3%を占め、死亡率は50%~100%にのぼる。とあるICU一施設からの報告では、起因菌が判明した市中肺炎のうち、緑膿菌によるものが三番目に多いという結果が得られている(一般的には、一番多いのが肺炎球菌、二番はレジオネラである)。以上に紹介したICUにおける調査には、起因菌を緑膿菌をと判定する方法に問題があり、細菌学検査で確定診断が得られた症例は44.4%~78.6%を占めるに過ぎない。
過去に行われた研究では、前回入院から今回の入院までの期間や、患者が医療関連肺炎の診断基準を満たすかどうかについては、きちんと記されていない。医療関連肺炎とは、前回入院から30日以内もしくは一年以内に発症した肺炎を指す。30日以内の発症例を医療関連肺炎と定義した研究では市中肺炎の17.1%、一年以内と定義した別の研究では4.8%が緑膿菌によるものであった。そして、医療関連肺炎のそれぞれ25.3%、25.5%が緑膿菌を起因菌とする肺炎であった。翻って、ドイツ市中肺炎ネットワークが行った5130名を対象とした前向き研究では、厳格な基準を設けて判定したところ、緑膿菌が起因菌であると同定されたのは22名であった。一名は血液から緑膿菌が分離され、残りの21名はグラム染色で診断された例である。発生頻度は0.4%(22/5130)ということになる。この22名の死亡率は18%であった。スペインで行われた市中肺炎患者780名についての前向き研究でも、緑膿菌が起因菌であった症例は少ないことが分かっている。
緑膿菌による市中肺炎の危険因子については、多くの知見が得られている。肺疾患、特にCOPDはいずれの研究においても危険因子であることが明らかにされている。その他の危険因子は、過去の入院歴、気管挿管および経腸栄養であり、いずれの場合も緑膿菌の定着が感染発症に先行することが分かっている。これらの危険因子を持つ場合は、正確には医療関連肺炎と分類すべきであろう。COPD and/or喫煙、HIV感染もしくは肺の構造に異常が生ずる疾患(気管支拡張症など)がある患者では、市中肺炎の起因菌が緑膿菌であることは珍しくない。
HIV陽性患者における緑膿菌肺炎
高活性抗レトロウイルス療法(HAART; highly active anti-retroviral therapy)が登場する以前は、HIV陽性成人ではHIV陰性成人と比べ、細菌性肺炎発生頻度が有意に高く(5.5 vs 0.9/100人年、P<0.01)、CD4リンパ球数が減るほど肺炎発生頻度が増えるとされていた。HARRT前の時代には、肺炎球菌が起因菌として最多であり(25%~46.7%)、緑膿菌は8%~25%を占めていた。院内肺炎の起因菌の中では緑膿菌が最多であった(21.4%~38.7%)。緑膿菌肺炎による死亡率は42%~55%で、他の起因菌による肺炎の死亡率よりも極めて高い。緑膿菌による市中肺炎を発症したHIV陽性患者16名の平均CD4リンパ球数は、わずか27/μLで、69%の患者において空洞性病変が胸部X線写真で認められた。好中球減少、最近の入院歴または抗菌薬使用歴といった典型的な危険因子を有する症例はなかった。ニューモシスティス肺炎の予防に使用するST合剤は、トキソプラズマ、サルモネラ、ヘモフィルス、黄色ブドウ球菌に対しても有効であるが、肺炎球菌、肺炎球菌以外の連鎖球菌および緑膿菌には無効である。
HAARTの登場によって、HIV感染症が進行した患者の合併症発生率および死亡率は劇的に低下した。しかし、HIV患者における細菌性肺炎の発生頻度は必ずしも低下しておらず、入院理由として最も多いのは依然として細菌性肺炎である。HAART時代の現在でも、市中肺炎の起因菌として最も多いのは肺炎球菌であり、緑膿菌は5%~6.7%を占める。緑膿菌がHIV患者における院内肺炎の起因菌として最多であるのは今も変わらず、緑膿菌院内肺炎の死亡率は23%である。緑膿菌肺炎患者のCD4リンパ球数は入院時の平均値は27~42/μLで、HAART前の時代と同等である。
教訓 緑膿菌による市中肺炎はまれです。ただし、COPD 、喫煙、HIV感染もしくは肺の構造に異常が生ずる疾患(気管支拡張症など)といった因子を持つ患者では、緑膿菌による市中肺炎は珍しくありません。
2011-07-12 07:17
コメント(0)
緑膿菌肺炎~疫学① [critical care]
Pneumonia Due to Pseudomonas aeruginosa
Part I: Epidemiology, Clinical Diagnosis, and Source
CHEST 2011年4月号より
緑膿菌はグラム陰性桿菌で自然界のどこにでも存在する日和見病原菌である。緑膿菌は非常に毒性の高い病原菌であり、菌体外毒素や酵素などの毒性物質を産生する。また、バイオフィルムを形成し、環境因子や宿主の抗体や食細胞から身を守ることもできる。緑膿菌肺炎が増加し、治療に新たな障壁が生じている現状を踏まえ、緑膿菌肺炎についてまとめたのが本レビューである。線維性嚢胞症患者における緑膿菌肺炎は、特有の気道病変と関連する特異的な感染症として扱うできであり、本レビューの範疇を超えるためここでは触れない。
歴史概観
緑膿菌はさまざまな解剖学的部位において感染を起こすが、なかでも肺の感染は最も死亡率が高い。肺の出血性病変や壊死性病変のある易感染性患者で発生するのが、緑膿菌肺炎の古典的典型例である。緑膿菌による呼吸器感染症は19世紀末には報告されているが、当時は非常に稀な疾患であった。菌血症を伴う緑膿菌肺炎の病理学的特徴はすでに1917年には報告され、血管の侵入と壊死が認められるとされた。そして、菌血症を伴わない緑膿菌肺炎では、微小膿瘍、出血および巣状壊死が認められることが報告されている。
臨床医は、緑膿菌による呼吸器感染症の分類をいくつか頭に入れておく必要がある。その第一が市中肺炎(CAP; community-acquired pneumonia)である。上気道への緑膿菌定着が、肺の感染へと進展したものを指す。線維性嚢胞症の小児や慢性肺疾患患者ではこのような機序で肺炎が成立すると考えられている。気管支拡張症に緑膿菌肺炎が合併するケースは現在では稀になった。第二は、ICU肺炎である。これはCAPよりも多いタイプの緑膿菌肺炎であり、(1)汚染された吸入液や人工呼吸器からの緑膿菌吸引、または(2)慢性肺疾患でもともと緑膿菌が定着していて入院後に肺炎が成立したものの二つに分けられる。第三は、免疫抑制患者における緑膿菌菌血症に伴う緑膿菌肺炎である。多くは好中球減少症があり血行性に肺に感染が広がる。治療に際しては以上の三つをはっきり区別することが重要である。抗菌薬の多剤併用療法が単剤使用よりも有効であることを示す報告の先鞭をつけたのは、血液悪性疾患で菌血症を呈する患者を対象とした研究だからである。
疫学
院内肺炎
1980年代後半にCDCの全国院内感染研究が行われ、院内感染のなかで緑膿菌肺炎が占める割合が徐々に増えていることが報告された。緑膿菌による院内肺炎は1975年から2003年の間に9.6%から18.1%へとほぼ2倍に増加した。米国に所在するICUを対象とした全国規模の大規模調査では、ICUで検出されるグラム陰性好気性菌のうちもっと多いのが緑膿菌で(23%、8244/35790)、呼吸器から分離される細菌としても最も多い(31.6%)。ピッツバーグ大学においてミニBALまたは気管支鏡検査で診断確定したVAP(人工呼吸器関連肺炎)670例のうち、最も多かった起因菌は緑膿菌であった(20%)。VAP症例842例を対象とした遡及的症例対照コホート研究が米国で行われ、人工呼吸開始4日目以降に発生したVAPでは、緑膿菌が起因菌として最も多かった(9.3%)。
緑膿菌によるVAPはたとえ適切な抗菌薬が投与されても死亡率が高く、粗死亡率は42.1%から87%、直接の死因とする場合の死亡率は32%から42.8%である(Table 1)。スペインに所在する27床を擁するICUにおいて、緑膿菌感染症集団発生に伴う経済負担の解析が行われた。患者17名が対象となり、大半が緑膿菌による気道感染があり死亡率は47%であった。緑膿菌感染によって余分にかかった費用は控えめに見積もっても421000米ドルであった。この金額には、検査、薬剤、ICU管理に伴う費用が含まれる。緑膿菌感染一例あたりかかる平均費用は24700米ドルであり、入院期間中央値は45日であった。
気管支鏡関連緑膿菌肺炎
緑膿菌による院内肺炎は医原性に発生することもある。複数の研究で、緑膿菌の感染源が汚染された気管支鏡であった例が報告されている。このような研究では、環境、気管支鏡および気管支鏡検査を受けた患者から検出された緑膿菌が、様々なサブタイプ解析で同一であることが明らかにされている(Table 2)。
気管支鏡が汚染する原因は、気管支鏡の欠陥・損傷や不適切な消毒手順である。汚染を広げる要因は、生検ポートの蓋のゆるみ(このために緑膿菌肺炎を複数患者に発生させ3名がそのため死亡したとみられる例がある)、壊れた生検鉗子による気管支鏡内腔の損傷、洗浄器による汚染、不適切な消毒などである。気管支鏡検査を受けた患者における緑膿菌感染集団発生もどきが発生したケースが二件報告されている。一件では8名、もう一件では41名の緑膿菌感染患者が発生したが、検出された緑膿菌の株は同一ではなかった。
教訓
緑膿菌によるVAPはたとえ適切な抗菌薬が投与されても粗死亡率は42.1%から87%にものぼります。気管支鏡から緑膿菌が蔓延することがあります。
CHEST 2011年4月号より
緑膿菌はグラム陰性桿菌で自然界のどこにでも存在する日和見病原菌である。緑膿菌は非常に毒性の高い病原菌であり、菌体外毒素や酵素などの毒性物質を産生する。また、バイオフィルムを形成し、環境因子や宿主の抗体や食細胞から身を守ることもできる。緑膿菌肺炎が増加し、治療に新たな障壁が生じている現状を踏まえ、緑膿菌肺炎についてまとめたのが本レビューである。線維性嚢胞症患者における緑膿菌肺炎は、特有の気道病変と関連する特異的な感染症として扱うできであり、本レビューの範疇を超えるためここでは触れない。
歴史概観
緑膿菌はさまざまな解剖学的部位において感染を起こすが、なかでも肺の感染は最も死亡率が高い。肺の出血性病変や壊死性病変のある易感染性患者で発生するのが、緑膿菌肺炎の古典的典型例である。緑膿菌による呼吸器感染症は19世紀末には報告されているが、当時は非常に稀な疾患であった。菌血症を伴う緑膿菌肺炎の病理学的特徴はすでに1917年には報告され、血管の侵入と壊死が認められるとされた。そして、菌血症を伴わない緑膿菌肺炎では、微小膿瘍、出血および巣状壊死が認められることが報告されている。
臨床医は、緑膿菌による呼吸器感染症の分類をいくつか頭に入れておく必要がある。その第一が市中肺炎(CAP; community-acquired pneumonia)である。上気道への緑膿菌定着が、肺の感染へと進展したものを指す。線維性嚢胞症の小児や慢性肺疾患患者ではこのような機序で肺炎が成立すると考えられている。気管支拡張症に緑膿菌肺炎が合併するケースは現在では稀になった。第二は、ICU肺炎である。これはCAPよりも多いタイプの緑膿菌肺炎であり、(1)汚染された吸入液や人工呼吸器からの緑膿菌吸引、または(2)慢性肺疾患でもともと緑膿菌が定着していて入院後に肺炎が成立したものの二つに分けられる。第三は、免疫抑制患者における緑膿菌菌血症に伴う緑膿菌肺炎である。多くは好中球減少症があり血行性に肺に感染が広がる。治療に際しては以上の三つをはっきり区別することが重要である。抗菌薬の多剤併用療法が単剤使用よりも有効であることを示す報告の先鞭をつけたのは、血液悪性疾患で菌血症を呈する患者を対象とした研究だからである。
疫学
院内肺炎
1980年代後半にCDCの全国院内感染研究が行われ、院内感染のなかで緑膿菌肺炎が占める割合が徐々に増えていることが報告された。緑膿菌による院内肺炎は1975年から2003年の間に9.6%から18.1%へとほぼ2倍に増加した。米国に所在するICUを対象とした全国規模の大規模調査では、ICUで検出されるグラム陰性好気性菌のうちもっと多いのが緑膿菌で(23%、8244/35790)、呼吸器から分離される細菌としても最も多い(31.6%)。ピッツバーグ大学においてミニBALまたは気管支鏡検査で診断確定したVAP(人工呼吸器関連肺炎)670例のうち、最も多かった起因菌は緑膿菌であった(20%)。VAP症例842例を対象とした遡及的症例対照コホート研究が米国で行われ、人工呼吸開始4日目以降に発生したVAPでは、緑膿菌が起因菌として最も多かった(9.3%)。
緑膿菌によるVAPはたとえ適切な抗菌薬が投与されても死亡率が高く、粗死亡率は42.1%から87%、直接の死因とする場合の死亡率は32%から42.8%である(Table 1)。スペインに所在する27床を擁するICUにおいて、緑膿菌感染症集団発生に伴う経済負担の解析が行われた。患者17名が対象となり、大半が緑膿菌による気道感染があり死亡率は47%であった。緑膿菌感染によって余分にかかった費用は控えめに見積もっても421000米ドルであった。この金額には、検査、薬剤、ICU管理に伴う費用が含まれる。緑膿菌感染一例あたりかかる平均費用は24700米ドルであり、入院期間中央値は45日であった。
気管支鏡関連緑膿菌肺炎
緑膿菌による院内肺炎は医原性に発生することもある。複数の研究で、緑膿菌の感染源が汚染された気管支鏡であった例が報告されている。このような研究では、環境、気管支鏡および気管支鏡検査を受けた患者から検出された緑膿菌が、様々なサブタイプ解析で同一であることが明らかにされている(Table 2)。
気管支鏡が汚染する原因は、気管支鏡の欠陥・損傷や不適切な消毒手順である。汚染を広げる要因は、生検ポートの蓋のゆるみ(このために緑膿菌肺炎を複数患者に発生させ3名がそのため死亡したとみられる例がある)、壊れた生検鉗子による気管支鏡内腔の損傷、洗浄器による汚染、不適切な消毒などである。気管支鏡検査を受けた患者における緑膿菌感染集団発生もどきが発生したケースが二件報告されている。一件では8名、もう一件では41名の緑膿菌感染患者が発生したが、検出された緑膿菌の株は同一ではなかった。
教訓
緑膿菌によるVAPはたとえ適切な抗菌薬が投与されても粗死亡率は42.1%から87%にものぼります。気管支鏡から緑膿菌が蔓延することがあります。
2011-07-11 07:38
コメント(0)
人工心肺とAKI~バイオマーカ [anesthesiology]
Cardiopulmonary Bypass–associated Acute Kidney Injury
Anesthesiology 2011年4月号より
急性腎傷害の早期診断:AKI-CPBにおけるバイオマーカの有用性
急性腎傷害の診断にもっとも一般的に用いられている検査項目は、血清クレアチニン値(sCr)である。血清クレアチニン値は糸球体濾過率の低下や改善よりも数日遅れて変化するため、腎機能の短期的変化を評価するには感度が低く信頼できないバイオマーカである。さらに、sCrは年齢、人種、筋肉量、分布容量、使用薬剤、タンパク摂取量などの影響を受けて変化する。また、腎傷害の種類を判別するのには役立たない(虚血性傷害か、腎前性傷害か、など)。したがって、急性腎傷害の早期診断に役立ち、できれば原因も含めた診断が可能で、治療効果を迅速に判定することのできる感度と特異度の高いバイオマーカの開発が急務である。
米国腎臓病学会は2005年に、急性腎傷害のバイオマーカの特定と解明を重要な研究課題として位置づけた。これが、急性腎傷害に関わる20種類以上のバイオマーカの特定と検討につながった。バイオマーカの性能は、ROC曲線下面積として表されるのが通例である。ROC曲線下面積が0.75以上の場合は診断能良好、0.90以上であれば極めて診断能が高いことを意味する。今後1~2年以内に実用化される可能性が高いバイオマーカについて、以下に簡潔に紹介する。
好中球ゼラチナーゼ関連リポカリン(NGAL)は、AKI-CPBの診断に有用なバイオマーカとして熱い視線を浴びている。腎機能正常患者では血漿、尿いずれにおいてもNGALはほぼ検出不能である。しかし急性尿細管傷害が発生すると、血漿中および尿中のNGALが増加する。小児心臓手術患者において、NGALがAKI-CPBのマーカとして感度も特異度も高いことが示されている。成人心臓手術患者におけるNGALの診断性能についての報告は一貫していない。なぜ相反する報告が存在するのか、その理由ははっきりしていない。人工心肺下心臓手術後の小児患者および成人患者では、人工心肺終了2時間後のNGAL血中濃度が150ng/mL以上の場合、AKI-CPB予測のROC曲線下面積は0.96で、感度84%、特異度94%である。人工心肺終了2時間後のNGAL濃度は、急性腎傷害の重症度と回復までに要する期間、および入院期間と強く相関する。さらに、人工心肺終了12時間後NGAL濃度と死亡率とのあいだに高い相関があることが分かっている。
人工心肺終了2時間後尿中NGAL濃度が100ng/mL以上の場合、AKI-CPBを発症する可能性が高い(ROC曲線下面積0.95、感度94%、特異度90%)。人工心肺終了2時間後尿中NGAL濃度は、急性腎傷害の重症度と回復までに要する期間、入院期間、透析実施率および死亡率と強く相関する。急性腎傷害以外の病態が、NGAL濃度にどのような影響をおよぼすかはまだ分かっていない。NGALを広く実用化するには、様々な特性を持つ患者群についての研究を実施しその有用性を検証する必要がある。
その他にもいくつかのバイオマーカに期待が寄せられている。例えば、シスタチンC、腎傷害因子1(KIM-1)、IL-18などである。シスタチンCは糸球体濾過率を反映するマーカになり得る。このバイオマーカは、年齢、性別および筋肉量には左右されないことが明らかにされている。過去に行われた研究では、シスタチンCの有用性を裏付ける結果、否定する結果のいずれもがあり、AKI-CPBの診断や予後予測に威力を発揮するかどうかは不明である。腎傷害因子1(KIM-1)はNGALと同様に、正常腎機能患者の尿中からは通常は検出されない。急性虚血性変化により近位尿細管においてKIM-1の顕著なアップレギュレーションが起こる。AKI-CPB患者におけるKIM-1の感度は低く(50%未満)、AKI-CPBの診断や管理における有用性は検証されていない。急性尿細管傷害は、人工心肺を含めいろいろな原因で発生する。このとき尿中IL-18濃度は大幅に上昇する。成人患者では尿中IL-18濃度は、AKI-CPB発症の有無ではなく人工心肺時間とよく相関する。つまり、IL-18は人工心肺による炎症のマーカであって、何らかの腎傷害のマーカとはなり得ないと考えられる。異なるバイオマーカを組み合わせて測定すれば、AKI-CPBの診断能が向上する可能性がある。AKI-CPBの早期診断および管理に資するバイオマーカの組合せについてのデータはまだ不足していて、何らかの推奨事項を提示できるような段階ではない。新しいバイオマーカの同定に血道が上げられているが、大半は臨床現場では使用できないものばかりである。そして、診断性能については研究によって大きなばらつきがあり、各バイオマーカの交絡要因はよく分かっていない。過去に行われた各種バイオマーカの評価研究では、もともと腎疾患のある患者は除外されているが、基礎疾患としての腎疾患はAKI-CPBの高リスク因子であり、このような患者でこそ早期診断と術前腎機能の評価が重要である。STARD(STAndards for Reporting of Diagnostic accuracy)研究で報告されている基準に達するレベルの、十分な検出力を備えた研究の実施が待たれる。
まとめ
腎代替療法や集中治療が進歩を遂げた一方で、AKI-CPBの顛末は芳しくなく死亡率は看過し得ないほど高いため、重大な問題として憂慮されている。周術期管理においては、高リスク患者の同定、心拍出量および腎灌流圧の維持および腎毒性のある薬剤の回避などを心がけなければならない。適応があればオフポンプ手術を選択したり、人工心肺時間を極力短縮したりすれば、AKI-CPBの発生頻度は低下し得る。今後は、早期診断および原因特定がバイオマーカの使用によって現在より容易になる可能性がある。人工心肺による炎症や細胞障害の理解が進み、炎症反応の調節が可能となり、人工心肺技術が向上すれば、いずれはAKI-CPBの発生や重症化を予防できるようになるであろう。
教訓 クレアチニンは糸球体濾過率の低下や改善よりも数日遅れて変化するため、腎機能の短期的変化を評価するには感度が低く信頼できないバイオマーカです。人工心肺終了2時間後の血中NGAL濃度は、急性腎傷害の重症度と回復までに要する期間、および入院期間と強く相関します。人工心肺終了12時間後NGAL濃度と死亡率とのあいだには強い相関があります。
Anesthesiology 2011年4月号より
急性腎傷害の早期診断:AKI-CPBにおけるバイオマーカの有用性
急性腎傷害の診断にもっとも一般的に用いられている検査項目は、血清クレアチニン値(sCr)である。血清クレアチニン値は糸球体濾過率の低下や改善よりも数日遅れて変化するため、腎機能の短期的変化を評価するには感度が低く信頼できないバイオマーカである。さらに、sCrは年齢、人種、筋肉量、分布容量、使用薬剤、タンパク摂取量などの影響を受けて変化する。また、腎傷害の種類を判別するのには役立たない(虚血性傷害か、腎前性傷害か、など)。したがって、急性腎傷害の早期診断に役立ち、できれば原因も含めた診断が可能で、治療効果を迅速に判定することのできる感度と特異度の高いバイオマーカの開発が急務である。
米国腎臓病学会は2005年に、急性腎傷害のバイオマーカの特定と解明を重要な研究課題として位置づけた。これが、急性腎傷害に関わる20種類以上のバイオマーカの特定と検討につながった。バイオマーカの性能は、ROC曲線下面積として表されるのが通例である。ROC曲線下面積が0.75以上の場合は診断能良好、0.90以上であれば極めて診断能が高いことを意味する。今後1~2年以内に実用化される可能性が高いバイオマーカについて、以下に簡潔に紹介する。
好中球ゼラチナーゼ関連リポカリン(NGAL)は、AKI-CPBの診断に有用なバイオマーカとして熱い視線を浴びている。腎機能正常患者では血漿、尿いずれにおいてもNGALはほぼ検出不能である。しかし急性尿細管傷害が発生すると、血漿中および尿中のNGALが増加する。小児心臓手術患者において、NGALがAKI-CPBのマーカとして感度も特異度も高いことが示されている。成人心臓手術患者におけるNGALの診断性能についての報告は一貫していない。なぜ相反する報告が存在するのか、その理由ははっきりしていない。人工心肺下心臓手術後の小児患者および成人患者では、人工心肺終了2時間後のNGAL血中濃度が150ng/mL以上の場合、AKI-CPB予測のROC曲線下面積は0.96で、感度84%、特異度94%である。人工心肺終了2時間後のNGAL濃度は、急性腎傷害の重症度と回復までに要する期間、および入院期間と強く相関する。さらに、人工心肺終了12時間後NGAL濃度と死亡率とのあいだに高い相関があることが分かっている。
人工心肺終了2時間後尿中NGAL濃度が100ng/mL以上の場合、AKI-CPBを発症する可能性が高い(ROC曲線下面積0.95、感度94%、特異度90%)。人工心肺終了2時間後尿中NGAL濃度は、急性腎傷害の重症度と回復までに要する期間、入院期間、透析実施率および死亡率と強く相関する。急性腎傷害以外の病態が、NGAL濃度にどのような影響をおよぼすかはまだ分かっていない。NGALを広く実用化するには、様々な特性を持つ患者群についての研究を実施しその有用性を検証する必要がある。
その他にもいくつかのバイオマーカに期待が寄せられている。例えば、シスタチンC、腎傷害因子1(KIM-1)、IL-18などである。シスタチンCは糸球体濾過率を反映するマーカになり得る。このバイオマーカは、年齢、性別および筋肉量には左右されないことが明らかにされている。過去に行われた研究では、シスタチンCの有用性を裏付ける結果、否定する結果のいずれもがあり、AKI-CPBの診断や予後予測に威力を発揮するかどうかは不明である。腎傷害因子1(KIM-1)はNGALと同様に、正常腎機能患者の尿中からは通常は検出されない。急性虚血性変化により近位尿細管においてKIM-1の顕著なアップレギュレーションが起こる。AKI-CPB患者におけるKIM-1の感度は低く(50%未満)、AKI-CPBの診断や管理における有用性は検証されていない。急性尿細管傷害は、人工心肺を含めいろいろな原因で発生する。このとき尿中IL-18濃度は大幅に上昇する。成人患者では尿中IL-18濃度は、AKI-CPB発症の有無ではなく人工心肺時間とよく相関する。つまり、IL-18は人工心肺による炎症のマーカであって、何らかの腎傷害のマーカとはなり得ないと考えられる。異なるバイオマーカを組み合わせて測定すれば、AKI-CPBの診断能が向上する可能性がある。AKI-CPBの早期診断および管理に資するバイオマーカの組合せについてのデータはまだ不足していて、何らかの推奨事項を提示できるような段階ではない。新しいバイオマーカの同定に血道が上げられているが、大半は臨床現場では使用できないものばかりである。そして、診断性能については研究によって大きなばらつきがあり、各バイオマーカの交絡要因はよく分かっていない。過去に行われた各種バイオマーカの評価研究では、もともと腎疾患のある患者は除外されているが、基礎疾患としての腎疾患はAKI-CPBの高リスク因子であり、このような患者でこそ早期診断と術前腎機能の評価が重要である。STARD(STAndards for Reporting of Diagnostic accuracy)研究で報告されている基準に達するレベルの、十分な検出力を備えた研究の実施が待たれる。
まとめ
腎代替療法や集中治療が進歩を遂げた一方で、AKI-CPBの顛末は芳しくなく死亡率は看過し得ないほど高いため、重大な問題として憂慮されている。周術期管理においては、高リスク患者の同定、心拍出量および腎灌流圧の維持および腎毒性のある薬剤の回避などを心がけなければならない。適応があればオフポンプ手術を選択したり、人工心肺時間を極力短縮したりすれば、AKI-CPBの発生頻度は低下し得る。今後は、早期診断および原因特定がバイオマーカの使用によって現在より容易になる可能性がある。人工心肺による炎症や細胞障害の理解が進み、炎症反応の調節が可能となり、人工心肺技術が向上すれば、いずれはAKI-CPBの発生や重症化を予防できるようになるであろう。
教訓 クレアチニンは糸球体濾過率の低下や改善よりも数日遅れて変化するため、腎機能の短期的変化を評価するには感度が低く信頼できないバイオマーカです。人工心肺終了2時間後の血中NGAL濃度は、急性腎傷害の重症度と回復までに要する期間、および入院期間と強く相関します。人工心肺終了12時間後NGAL濃度と死亡率とのあいだには強い相関があります。
2011-07-08 07:37
コメント(0)
人工心肺とAKI~周術期管理② [anesthesiology]
Cardiopulmonary Bypass–associated Acute Kidney Injury
Anesthesiology 2011年4月号より
AKI-CPBを防ぐには、腎血流を増やす薬剤の投与も一法である。複数の薬剤が研究対象となっている。選択的ドパミンD1受容体作動薬のフェノルドパムは、比較対照のない小規模試験でAKI-CPBの発生頻度を減らす効果があるとされている。フェノルドパムには腎血管拡張という好ましい作用があるが、この効果は低血圧によって打ち消されてしまう可能性がある。カテーテルを用いてフェノルドパムを腎血管内に直接投与するという画期的な方法についての研究が現在進行中である。本剤の使用を広く推奨するには、信頼性の高い研究を積み重ね有効性を証明する必要がある。
CPBによる炎症と酸化ストレスを軽減するためNアセチルシステインを投与する、という薬物療法も取り上げられている。しかし、最近の複数の研究やメタ分析では、NアセチルシステインにAKI-CPBを予防する効果はないという結果が示されている。したがって、Nアセチルシステインのルーチーン使用は推奨されない。
術後早期に全身水分量を調節するのに最も頻用されているのは利尿薬である。利尿薬には(尿量を増やすことによって)腎尿細管の閉塞を防ぎ、尿細管上皮細胞の酸素消費量を減らし急性腎傷害を軽減する作用があると理論上は考えられている。しかし、臨床研究では術後早期にルーチーンで利尿薬を投与(持続静注を含む)しても、AKI-CPBを防ぐことはできないことが示されている。同様に、ドパミンの少量投与(1-3mcg/kg/min)による腎血流量増加が急性腎傷害の予防につながるか否か、という問題についても長年の間活発な議論が繰り広げられてきた。ドパミン少量投与にはAKI-CPB予防効果はないことが、数多くの研究で明らかにされている。AKI-CPBの治療や予防にドパミンや積極的な利尿薬投与の出る幕はない、というのが現在までに蓄積されたエビデンスから導かれる結論である。
人工心肺手術を受ける患者のうち急性腎傷害を発症する危険性の高い患者では、腎代替療法の予防的実施が治療の選択肢となり得るのではないかという意見がある。腎代替療法の予防的実施がAKI-CPBの発生を抑制できるかどうかを検討した過去の諸研究は、腎代替療法実施開始基準が一貫していないため比較検討するのが困難である。また、単一施設研究も複数行われているが、検出力不足のためAKI-CPBの転帰の検証には無理がある。大規模臨床試験を行い実施基準が標準化されれば、将来的には腎代替療法の予防的実施が有効な選択肢となるかもしれない。AKI-CPBの病態生理機序と、その予防を目指した管理方針をfigure 1にまとめた。
その他の管理法
人工心肺の影響を極力少なくしたり、人工心肺の使用自体を避けたりする手術法についての研究が盛んに行われている。心臓外科において「オフポンプ(人工心肺非使用)」手術や「心拍動下」手術が発展したのは1990年代のことである。この手法では拍動流が維持されるとともに、人工心肺回路という異物との血液の接触がないため、炎症性サイトカインの放出が減る。「オンポンプ」手術よりもオフポンプ手術の方が優れていることを示した古い研究の大半は、単一施設研究で無作為化割り当ても行われていない。また、術前の急性腎傷害発症リスクがばらばらの均質でない母集団を対象としているため、本術式による急性腎傷害のリスクを判断することは難しい。以上のような問題があるものの、現在までに蓄積されたデータの多くがオフポンプ手術はオンポンプ手術よりも急性腎傷害のリスクが小さいことを示している。実際、AHAは従来の人工心肺下手術と比べ人工心肺非使用手術の方が腎関連リスクが小さいという見解を示している。
旧来の人工心肺の欠点を極力避けつつオンポンプ手術の利便性を活かす小型人工心肺装置に注目が集まっている。小型人工心肺装置はヘパリンコーティングチューブと人工肺で構成されている。そして、充填容量(プライミングボリューム)が少なく、吸引回路と静脈リザーバがない。この閉鎖式小型人工心肺装置には静脈リザーバがないため、従来型の人工心肺を用いる場合よりも血管内容量が減少せず、平均動脈圧が下がらないという効果が期待されている。小型人工心肺装置では血液希釈が軽度にとどまるため、赤血球輸血が必要となる頻度が減る可能性がある。以上の利点が直接的、間接的に腎保護作用を発揮すると考えられる。
術式を選択する際は、対象患者を適切に選別し、各術者の経験・技量および当該施設における過去の症例数を考慮すべきである。
教訓 Nアセチルシステイン、利尿薬、ドパミン少量投与にはAKI-CPBを防ぐ効果はないようです。
Anesthesiology 2011年4月号より
AKI-CPBを防ぐには、腎血流を増やす薬剤の投与も一法である。複数の薬剤が研究対象となっている。選択的ドパミンD1受容体作動薬のフェノルドパムは、比較対照のない小規模試験でAKI-CPBの発生頻度を減らす効果があるとされている。フェノルドパムには腎血管拡張という好ましい作用があるが、この効果は低血圧によって打ち消されてしまう可能性がある。カテーテルを用いてフェノルドパムを腎血管内に直接投与するという画期的な方法についての研究が現在進行中である。本剤の使用を広く推奨するには、信頼性の高い研究を積み重ね有効性を証明する必要がある。
CPBによる炎症と酸化ストレスを軽減するためNアセチルシステインを投与する、という薬物療法も取り上げられている。しかし、最近の複数の研究やメタ分析では、NアセチルシステインにAKI-CPBを予防する効果はないという結果が示されている。したがって、Nアセチルシステインのルーチーン使用は推奨されない。
術後早期に全身水分量を調節するのに最も頻用されているのは利尿薬である。利尿薬には(尿量を増やすことによって)腎尿細管の閉塞を防ぎ、尿細管上皮細胞の酸素消費量を減らし急性腎傷害を軽減する作用があると理論上は考えられている。しかし、臨床研究では術後早期にルーチーンで利尿薬を投与(持続静注を含む)しても、AKI-CPBを防ぐことはできないことが示されている。同様に、ドパミンの少量投与(1-3mcg/kg/min)による腎血流量増加が急性腎傷害の予防につながるか否か、という問題についても長年の間活発な議論が繰り広げられてきた。ドパミン少量投与にはAKI-CPB予防効果はないことが、数多くの研究で明らかにされている。AKI-CPBの治療や予防にドパミンや積極的な利尿薬投与の出る幕はない、というのが現在までに蓄積されたエビデンスから導かれる結論である。
人工心肺手術を受ける患者のうち急性腎傷害を発症する危険性の高い患者では、腎代替療法の予防的実施が治療の選択肢となり得るのではないかという意見がある。腎代替療法の予防的実施がAKI-CPBの発生を抑制できるかどうかを検討した過去の諸研究は、腎代替療法実施開始基準が一貫していないため比較検討するのが困難である。また、単一施設研究も複数行われているが、検出力不足のためAKI-CPBの転帰の検証には無理がある。大規模臨床試験を行い実施基準が標準化されれば、将来的には腎代替療法の予防的実施が有効な選択肢となるかもしれない。AKI-CPBの病態生理機序と、その予防を目指した管理方針をfigure 1にまとめた。
その他の管理法
人工心肺の影響を極力少なくしたり、人工心肺の使用自体を避けたりする手術法についての研究が盛んに行われている。心臓外科において「オフポンプ(人工心肺非使用)」手術や「心拍動下」手術が発展したのは1990年代のことである。この手法では拍動流が維持されるとともに、人工心肺回路という異物との血液の接触がないため、炎症性サイトカインの放出が減る。「オンポンプ」手術よりもオフポンプ手術の方が優れていることを示した古い研究の大半は、単一施設研究で無作為化割り当ても行われていない。また、術前の急性腎傷害発症リスクがばらばらの均質でない母集団を対象としているため、本術式による急性腎傷害のリスクを判断することは難しい。以上のような問題があるものの、現在までに蓄積されたデータの多くがオフポンプ手術はオンポンプ手術よりも急性腎傷害のリスクが小さいことを示している。実際、AHAは従来の人工心肺下手術と比べ人工心肺非使用手術の方が腎関連リスクが小さいという見解を示している。
旧来の人工心肺の欠点を極力避けつつオンポンプ手術の利便性を活かす小型人工心肺装置に注目が集まっている。小型人工心肺装置はヘパリンコーティングチューブと人工肺で構成されている。そして、充填容量(プライミングボリューム)が少なく、吸引回路と静脈リザーバがない。この閉鎖式小型人工心肺装置には静脈リザーバがないため、従来型の人工心肺を用いる場合よりも血管内容量が減少せず、平均動脈圧が下がらないという効果が期待されている。小型人工心肺装置では血液希釈が軽度にとどまるため、赤血球輸血が必要となる頻度が減る可能性がある。以上の利点が直接的、間接的に腎保護作用を発揮すると考えられる。
術式を選択する際は、対象患者を適切に選別し、各術者の経験・技量および当該施設における過去の症例数を考慮すべきである。
教訓 Nアセチルシステイン、利尿薬、ドパミン少量投与にはAKI-CPBを防ぐ効果はないようです。
2011-07-07 07:33
コメント(0)
人工心肺とAKI~周術期管理① [anesthesiology]
Cardiopulmonary Bypass–associated Acute Kidney Injury
Anesthesiology 2011年4月号より
AKI-CPB(人工心肺関連急性腎傷害)の周術期管理
術前における主な留意点は、適正な血管内容量および心拍出量の維持と鬱血性心不全の治療である。NSAIDsなどの腎毒性物質は中止し、造影剤はできる限り使用しないようにすべきである。AKI-CPBを防ぐためACEIやARBを術前に中止すべきかどうか、という問題については賛否両論があり決着はついていない。
改善可能な危険因子の大半について介入することが可能なのが術中である。人工心肺中は組織血流を適正に保つことが最も重要であり、そのために平均動脈圧と人工心肺灌流量を調節する。通常の人工心肺灌流量は2.2~2.5L/min/m2である(正常ヘモグロビン濃度、正常ヘマトクリットの正常体温成人の心係数に近い値)。たいていの施設では人工心肺中の平均動脈圧は50~70mmHgの範囲で管理している。腎傷害を防ぐという観点で、人工心肺中の灌流量および平均動脈圧をどれぐらい以上に保てばいいのか、という疑問に対する答えにつながるエビデンスは不足している。人工心肺を回すと血液が希釈されるため、理論的には血液粘度の低下により臓器血流が増加し、微小循環も改善する可能性がある。しかし、最近発表された4編の研究では、人工心肺中のヘマトクリットが21-24%を下回ると急性腎傷害の発生頻度が有意に上昇することが示されている。米国胸部外科学会および米国心臓外科麻酔学会が制定した輸血・貯血ガイドラインでは、現行のエビデンスを踏まえ、人工心肺中はヘマトクリットを21%以上(ヘモグロビン7g/dL以上)に維持することが推奨されている。
人工心肺時間が延長するほどAKI-CPB発症しやすいという独立した相関があることが明らかにされている。人工心肺が長引くほど、凝固能障害、輸血実施、消化管血流の低下および急性腎傷害の危険性が増大する。人工心肺時間がこれ以上延長すると急性腎傷害の発症頻度が急増する、という閾値として定まった一つの目安はない。いずれは、AKI-CPBを起こし難い「安全な人工心肺時間」が研究の積み重ねの結果明らかになるであろう。
集中治療領域において厳格血糖管理(血糖値を80-110mg/dLに維持する)を行うと転帰が有意に改善することを示した画期的な研究が発表され、血糖値管理と転帰の関係に改めて注目が集まっている。だが、その後に行われた心臓手術患者を対象とした二編の無作為化比較対照試験では、術中血糖値が正常範囲となるように積極的な管理が行われた群では転帰が悪化するという結果が得られた。術中および術後早期の高血糖(血糖値>200mg/dL)および術後の血糖値変動幅が大きいことの方が、厳格血糖管理実施の有無よりも、転帰悪化(腎機能の悪化を含む)の有力な予測因子であることが分かっている。最近のエビデンスでは、周術期血糖値は、厳格血糖管理で示されているような目標値にするのではなく、180mg/dL未満かつ変動が大きくならないように管理すべきである、とされている。
AKI-CPBの発生の予防につながる術後管理法を模索するため、様々な薬物投与や治療方針が試みられている。当初行われた研究ではこのうちの一部が有効であることが期待されたが、広く普及することを後押しするような決定的なエビデンスはない。新しく行われた複数の臨床試験で遺伝子組み換え心房性ナトリウム利尿ペプチドが有望であることが示されたことを受け、本剤に改めて注目が集まっている。心房性ナトリウム利尿ペプチドは、糸球体濾過率を増加させ、集合管におけるナトリウム再吸収を阻害することによってナトリウム利尿をもたらす。先頃行われた研究では、心房性ナトリウム利尿ペプチドの少量投与によって非代償性鬱血性心不全患者の人工心肺後透析実施率が低下し、透析非実施21日後生存率が上昇するという結果が得られた。ネシリチド(遺伝子組み換えヒトBNP)は心房性ナトリウム利尿ペプチドの一種で、腎血流を減らさずにナトリウム利尿効果を発揮する。Nesiritide Administered Peri-Anesthesia in Patients Undergoing Cardiac Surgery(NAPA)という臨床試験では、ネシリチドに短期的な腎機能保護効果があることが示された。具体的には、血清クレアチニン値の上昇幅が抑えられ、糸球体濾過率が低下せず、手術24時間後までの尿量が非投与群より多い、という結果が得られた。心房性ナトリウム利尿ペプチドの少量投与やネシリチドが有効であることを示唆するデータは報告されているが、あらゆる患者にナトリウム利尿効果のある薬剤を投与することを推奨するには、まだ知見が不足している。
教訓 AKI-CPBを防ぐには、人工心肺中は平均動脈圧と人工心肺灌流量を適切に維持しなければなりません。人工心肺中のヘマトクリットが21-24%を下回ると急性腎傷害の発生頻度が有意に上昇します。ハンプにはAKI-CPBを防ぐ効果があるかもしれません。
Anesthesiology 2011年4月号より
AKI-CPB(人工心肺関連急性腎傷害)の周術期管理
術前における主な留意点は、適正な血管内容量および心拍出量の維持と鬱血性心不全の治療である。NSAIDsなどの腎毒性物質は中止し、造影剤はできる限り使用しないようにすべきである。AKI-CPBを防ぐためACEIやARBを術前に中止すべきかどうか、という問題については賛否両論があり決着はついていない。
改善可能な危険因子の大半について介入することが可能なのが術中である。人工心肺中は組織血流を適正に保つことが最も重要であり、そのために平均動脈圧と人工心肺灌流量を調節する。通常の人工心肺灌流量は2.2~2.5L/min/m2である(正常ヘモグロビン濃度、正常ヘマトクリットの正常体温成人の心係数に近い値)。たいていの施設では人工心肺中の平均動脈圧は50~70mmHgの範囲で管理している。腎傷害を防ぐという観点で、人工心肺中の灌流量および平均動脈圧をどれぐらい以上に保てばいいのか、という疑問に対する答えにつながるエビデンスは不足している。人工心肺を回すと血液が希釈されるため、理論的には血液粘度の低下により臓器血流が増加し、微小循環も改善する可能性がある。しかし、最近発表された4編の研究では、人工心肺中のヘマトクリットが21-24%を下回ると急性腎傷害の発生頻度が有意に上昇することが示されている。米国胸部外科学会および米国心臓外科麻酔学会が制定した輸血・貯血ガイドラインでは、現行のエビデンスを踏まえ、人工心肺中はヘマトクリットを21%以上(ヘモグロビン7g/dL以上)に維持することが推奨されている。
人工心肺時間が延長するほどAKI-CPB発症しやすいという独立した相関があることが明らかにされている。人工心肺が長引くほど、凝固能障害、輸血実施、消化管血流の低下および急性腎傷害の危険性が増大する。人工心肺時間がこれ以上延長すると急性腎傷害の発症頻度が急増する、という閾値として定まった一つの目安はない。いずれは、AKI-CPBを起こし難い「安全な人工心肺時間」が研究の積み重ねの結果明らかになるであろう。
集中治療領域において厳格血糖管理(血糖値を80-110mg/dLに維持する)を行うと転帰が有意に改善することを示した画期的な研究が発表され、血糖値管理と転帰の関係に改めて注目が集まっている。だが、その後に行われた心臓手術患者を対象とした二編の無作為化比較対照試験では、術中血糖値が正常範囲となるように積極的な管理が行われた群では転帰が悪化するという結果が得られた。術中および術後早期の高血糖(血糖値>200mg/dL)および術後の血糖値変動幅が大きいことの方が、厳格血糖管理実施の有無よりも、転帰悪化(腎機能の悪化を含む)の有力な予測因子であることが分かっている。最近のエビデンスでは、周術期血糖値は、厳格血糖管理で示されているような目標値にするのではなく、180mg/dL未満かつ変動が大きくならないように管理すべきである、とされている。
AKI-CPBの発生の予防につながる術後管理法を模索するため、様々な薬物投与や治療方針が試みられている。当初行われた研究ではこのうちの一部が有効であることが期待されたが、広く普及することを後押しするような決定的なエビデンスはない。新しく行われた複数の臨床試験で遺伝子組み換え心房性ナトリウム利尿ペプチドが有望であることが示されたことを受け、本剤に改めて注目が集まっている。心房性ナトリウム利尿ペプチドは、糸球体濾過率を増加させ、集合管におけるナトリウム再吸収を阻害することによってナトリウム利尿をもたらす。先頃行われた研究では、心房性ナトリウム利尿ペプチドの少量投与によって非代償性鬱血性心不全患者の人工心肺後透析実施率が低下し、透析非実施21日後生存率が上昇するという結果が得られた。ネシリチド(遺伝子組み換えヒトBNP)は心房性ナトリウム利尿ペプチドの一種で、腎血流を減らさずにナトリウム利尿効果を発揮する。Nesiritide Administered Peri-Anesthesia in Patients Undergoing Cardiac Surgery(NAPA)という臨床試験では、ネシリチドに短期的な腎機能保護効果があることが示された。具体的には、血清クレアチニン値の上昇幅が抑えられ、糸球体濾過率が低下せず、手術24時間後までの尿量が非投与群より多い、という結果が得られた。心房性ナトリウム利尿ペプチドの少量投与やネシリチドが有効であることを示唆するデータは報告されているが、あらゆる患者にナトリウム利尿効果のある薬剤を投与することを推奨するには、まだ知見が不足している。
教訓 AKI-CPBを防ぐには、人工心肺中は平均動脈圧と人工心肺灌流量を適切に維持しなければなりません。人工心肺中のヘマトクリットが21-24%を下回ると急性腎傷害の発生頻度が有意に上昇します。ハンプにはAKI-CPBを防ぐ効果があるかもしれません。
2011-07-06 08:26
コメント(0)
人工心肺とAKI~病因とリスク [anesthesiology]
Cardiopulmonary Bypass–associated Acute Kidney Injury
Anesthesiology 2011年4月号より
AKI-CPBの病因
AKI-CPB(人工心肺関連急性腎傷害)の病態生理は、いろいろな要素が絡み合う複雑な様相を呈している。腎灌流圧の低下、炎症促進メディエイタの活性化、および腎毒性物質が、AKI-CPBの主な病因である。人工心肺を回すと、SIRS、腎臓の局所血流や血管抵抗の変化および微小塞栓の形成などを引き起こし、AKIの病因を生む。血球成分が人工物である人工心肺回路表面と接触することが、人工心肺によるSIRSの主な原因である。TNFα、IL-6およびIL-8がAKI-CPBの発症に関わる鍵となるサイトカインであると言われているが、その役割の本体はまだはっきりしていない。人工心肺を開始すると、血管抵抗が変化するため実効腎灌流圧は最大30%低下し、腎髄質の酸素分圧も低下する。その結果、虚血再灌流傷害が起こる。人工心肺を回すと溶血と補体タンパク活性化も引き起こされ、SIRSや虚血再灌流傷害の増悪要因となる。人工心肺中には微小塞栓が形成される。その成分は、フィブリン、血小板集塊、細胞破壊片、脂肪および空気などである。人工心肺回路のフィルタで、直径40μm以上の塞栓子は除去される。しかし、それより小さい塞栓子は通り抜けてしまうため、腎毛細血管にそのまま到達して害を及ぼす。以上とは別の病態生理の関与も指摘されている。たとえば、遊離鉄による毒性によって発生すると言われている色素性腎症や鉄腎症である。人工心肺によって遊離赤血球成分(ヘモグロビンおよび鉄)の血中濃度が上昇し、トランスフェリンやハプトグロビンなどの除去物質が消費されると、全血管抵抗および血小板機能が変化し、尿細管障害が発生する。
人工心肺を使用する心臓手術と比べ、人工心肺を使用しない心臓手術の方がAKI発生頻度が低いことから、AKI-CPBにおいて人工心肺が重大な要因であることは言を俟たない。
AKI-CPB発症リスクの見極め
AKI-CPB(人工心肺関連急性腎傷害)が発症するおそれのある患者を早い段階で見極めることが、周術期管理の質の向上につながる重要な対策の一つである。今までに少なくとも5種類のAKI-CPBリスク予測モデルが構築、検証されている。これまでに発表されたAKI-CPBリスク予測モデルにおいて取り上げられている主な危険因子をtable 2にまとめた。この中には、非心臓手術のAKIリスク予測モデルにおいて危険因子として取り上げられている因子(高齢、腎疾患の既往、糖尿病およびCOPD)も含まれている。
術前の血清クレアチニン(sCr)高値は、現時点では最も強力なAKI-CPB危険因子である。術前sCrが2.0-4.0mg/dLの患者のうち10-20%、4.0mg/dL以上の患者のうち約25%が、AKIを発症し透析を要する。その他の主な危険因子のうち患者に関係するものは、女性、左室駆出率40%未満、糖尿病、術前のIABP使用および緊急手術を要する状態である。患者側危険因子の大半が、介入によって変化させることができるとしてもほんのわずかしか改善の見込みがない、というところが興味深い。
手術に関連する危険因子に関しては、CABGのみの手術と比べ弁手術が高リスクであることが重要である。CABGと弁の同時手術がAKI-CPBのリスクが最も高い。緊急手術および強心薬/器械補助を要する周術期低心拍出量状態もAKI-CPBの発症リスクが上昇する要因である。AKI-CPBの発症リスクを正確に予測することができれば、早期診断及び治療の方策を確立する一助となる。
教訓 AKI-CPBの発症には、腎灌流圧の低下、炎症促進メディエイタの活性化、腎毒性物質、遊離鉄による毒性などが関与していると言われています。危険因子は、術前クレアチニン高値、女性、EF<40%、糖尿病、IABP、緊急手術、CABGとバルブの同時手術などです。
Anesthesiology 2011年4月号より
AKI-CPBの病因
AKI-CPB(人工心肺関連急性腎傷害)の病態生理は、いろいろな要素が絡み合う複雑な様相を呈している。腎灌流圧の低下、炎症促進メディエイタの活性化、および腎毒性物質が、AKI-CPBの主な病因である。人工心肺を回すと、SIRS、腎臓の局所血流や血管抵抗の変化および微小塞栓の形成などを引き起こし、AKIの病因を生む。血球成分が人工物である人工心肺回路表面と接触することが、人工心肺によるSIRSの主な原因である。TNFα、IL-6およびIL-8がAKI-CPBの発症に関わる鍵となるサイトカインであると言われているが、その役割の本体はまだはっきりしていない。人工心肺を開始すると、血管抵抗が変化するため実効腎灌流圧は最大30%低下し、腎髄質の酸素分圧も低下する。その結果、虚血再灌流傷害が起こる。人工心肺を回すと溶血と補体タンパク活性化も引き起こされ、SIRSや虚血再灌流傷害の増悪要因となる。人工心肺中には微小塞栓が形成される。その成分は、フィブリン、血小板集塊、細胞破壊片、脂肪および空気などである。人工心肺回路のフィルタで、直径40μm以上の塞栓子は除去される。しかし、それより小さい塞栓子は通り抜けてしまうため、腎毛細血管にそのまま到達して害を及ぼす。以上とは別の病態生理の関与も指摘されている。たとえば、遊離鉄による毒性によって発生すると言われている色素性腎症や鉄腎症である。人工心肺によって遊離赤血球成分(ヘモグロビンおよび鉄)の血中濃度が上昇し、トランスフェリンやハプトグロビンなどの除去物質が消費されると、全血管抵抗および血小板機能が変化し、尿細管障害が発生する。
人工心肺を使用する心臓手術と比べ、人工心肺を使用しない心臓手術の方がAKI発生頻度が低いことから、AKI-CPBにおいて人工心肺が重大な要因であることは言を俟たない。
AKI-CPB発症リスクの見極め
AKI-CPB(人工心肺関連急性腎傷害)が発症するおそれのある患者を早い段階で見極めることが、周術期管理の質の向上につながる重要な対策の一つである。今までに少なくとも5種類のAKI-CPBリスク予測モデルが構築、検証されている。これまでに発表されたAKI-CPBリスク予測モデルにおいて取り上げられている主な危険因子をtable 2にまとめた。この中には、非心臓手術のAKIリスク予測モデルにおいて危険因子として取り上げられている因子(高齢、腎疾患の既往、糖尿病およびCOPD)も含まれている。
術前の血清クレアチニン(sCr)高値は、現時点では最も強力なAKI-CPB危険因子である。術前sCrが2.0-4.0mg/dLの患者のうち10-20%、4.0mg/dL以上の患者のうち約25%が、AKIを発症し透析を要する。その他の主な危険因子のうち患者に関係するものは、女性、左室駆出率40%未満、糖尿病、術前のIABP使用および緊急手術を要する状態である。患者側危険因子の大半が、介入によって変化させることができるとしてもほんのわずかしか改善の見込みがない、というところが興味深い。
手術に関連する危険因子に関しては、CABGのみの手術と比べ弁手術が高リスクであることが重要である。CABGと弁の同時手術がAKI-CPBのリスクが最も高い。緊急手術および強心薬/器械補助を要する周術期低心拍出量状態もAKI-CPBの発症リスクが上昇する要因である。AKI-CPBの発症リスクを正確に予測することができれば、早期診断及び治療の方策を確立する一助となる。
教訓 AKI-CPBの発症には、腎灌流圧の低下、炎症促進メディエイタの活性化、腎毒性物質、遊離鉄による毒性などが関与していると言われています。危険因子は、術前クレアチニン高値、女性、EF<40%、糖尿病、IABP、緊急手術、CABGとバルブの同時手術などです。
2011-07-05 07:09
コメント(0)
人工心肺とAKI~定義 [anesthesiology]
Cardiopulmonary Bypass–associated Acute Kidney Injury
Anesthesiology 2011年4月号より
米国では毎年およそ30万人に心臓手術が行われている。通常行われる心臓手術の80%以上で人工心肺が用いられている。急性腎傷害(AKI;従来は急性腎不全と称されていた)が人工心肺後に発生することがあり、それ自体はよく知られているものの、詳細は十分には解明されていない。人工心肺関連急性腎傷害(AKI-CPB)は、短期転帰および長期転帰に重大な影響をおよぼす。AKI-CPB発症例では、非発症例と比べ、感染性合併症の増加、入院期間の延長、死亡率の上昇といった転帰の悪化を認める。AKI-CPBの発生頻度は、適用する診断分類の違いや術後いつまでを研究対象期間とするかによって差があるが、平均20-30%である。そして、AKI-CPBを発症し透析を要し、急性期を脱した後に維持透析に移行する症例が増えている。人工心肺下心臓手術のうち、CABGのみの手術がAKI-CPB発症リスクがもっとも小さく、弁置換術はCABGよりリスクが高い。そして、CABGと弁置換の同時手術が最も高リスクである。AKI-CPBの病態生理から見た原因や薬物治療について数多くの新しい知見が蓄積されているのとは裏腹に、死亡率はそれほど低下していない。その上、腎代替療法が進歩を見せているのに、AKI-CPBに関連する全死亡率は従来とさして変わらない。
本総説のテーマは、現行のAKI分類、病態生理およびAKI-CPB発症の危険因子である。さらに、本総説をAKI-CPB発症リスクのある患者の治療成績の向上につなげるべく、周術期管理法についても触れ、AKI-CPBという複雑な病態の理解を深める一助となる新しい概念を紹介する。
急性腎傷害(AKI)の定義
AKIの診断は一筋縄ではいかない。これまで用いられてきた定義や診断基準は一つではなく、基準時点の血清クレアチニン値(sCr)より25%以上上昇した場合をAKIとするものから、血液透析を要するほどになったものをAKIとして分類するものまで、幅広い考え方が存在していた。AKIの早期診断と重症度分類についての統一的定義が必要であったため、Acute Dialysis Quality InitiativeはRisk-Injury-Failure-Loss-End stage kidney disease(RIFLE)分類を制定した。そして、Acute Kidney Injury Network(AKIN)はRIFLE分類を改変し、さらに進化させたAKIN分類を構築した。RIFLE分類とAKIN分類は、心臓手術後のAKI患者を対象とした前向き研究で用いられ、その妥当性が検証されている。
RIFLE分類とAKIN分類との違いは、微々たるものである。AKIN分類では段階1にsCrが基準時点より0.3mg/dL以上上昇した患者も含め、対象患者の範囲を広げた。これは、たとえわずかでもsCrが上昇すると転帰が悪化するというエビデンスが蓄積されてきたことを踏まえての改変である。一方、RIFLE分類の危険群(AKIN分類の段階1に当たる)は、sCrが基準時点より50%以上上昇した場合となっている。重症患者では特に、尿量の変化がsCrの上昇よりも先行することがあるため、両分類とも尿量についての基準を設けている。AKIN分類では腎機能評価のための観察期間は48時間以内としているが、RIFLE分類では7日間以内である。AKIN分類で48時間以内という制限を設けた理由は、入院患者ではクレアチニンが24-48時間以内のあいだに上昇すると転帰不良であることを示すエビデンスが示されているからである。尿量やsCrに関わらず腎代替療法が行われている患者は、AKIN分類では段階3に相当する。一方、RIFLE分類では腎代替療法の実施期間に応じて、「loss(腎機能喪失)」群または「ESKD(末期腎不全)」群のいずれかに分類される。腎機能喪失群および末期腎不全群に相当するものはAKIN分類にはない。なぜなら、この二つは短期間の腎機能低下の程度を反映する分類ではなく、むしろ何らかの疾患の長期経過の末の転帰または慢性期の状態を反映するものだからである。
RIFLE分類、AKIN分類のいずれにも問題点がある。どちらも腎傷害の部位(尿細管傷害、糸球体傷害など)には言及していない。また、両分類とも血清クレアチニン値を大層重視しているが、この値自体は必ずしもAKIのバイオマーカとして適確ではない。AKI-CPB患者に適用するのにRIFLE分類とAKIN分類のどちらが有用であるかということに関して、はっきりとした一般見解は形成されていない。両分類の概略をtable 1に示した。
教訓 AKI-CPBの発生頻度は平均20-30%です。
Anesthesiology 2011年4月号より
米国では毎年およそ30万人に心臓手術が行われている。通常行われる心臓手術の80%以上で人工心肺が用いられている。急性腎傷害(AKI;従来は急性腎不全と称されていた)が人工心肺後に発生することがあり、それ自体はよく知られているものの、詳細は十分には解明されていない。人工心肺関連急性腎傷害(AKI-CPB)は、短期転帰および長期転帰に重大な影響をおよぼす。AKI-CPB発症例では、非発症例と比べ、感染性合併症の増加、入院期間の延長、死亡率の上昇といった転帰の悪化を認める。AKI-CPBの発生頻度は、適用する診断分類の違いや術後いつまでを研究対象期間とするかによって差があるが、平均20-30%である。そして、AKI-CPBを発症し透析を要し、急性期を脱した後に維持透析に移行する症例が増えている。人工心肺下心臓手術のうち、CABGのみの手術がAKI-CPB発症リスクがもっとも小さく、弁置換術はCABGよりリスクが高い。そして、CABGと弁置換の同時手術が最も高リスクである。AKI-CPBの病態生理から見た原因や薬物治療について数多くの新しい知見が蓄積されているのとは裏腹に、死亡率はそれほど低下していない。その上、腎代替療法が進歩を見せているのに、AKI-CPBに関連する全死亡率は従来とさして変わらない。
本総説のテーマは、現行のAKI分類、病態生理およびAKI-CPB発症の危険因子である。さらに、本総説をAKI-CPB発症リスクのある患者の治療成績の向上につなげるべく、周術期管理法についても触れ、AKI-CPBという複雑な病態の理解を深める一助となる新しい概念を紹介する。
急性腎傷害(AKI)の定義
AKIの診断は一筋縄ではいかない。これまで用いられてきた定義や診断基準は一つではなく、基準時点の血清クレアチニン値(sCr)より25%以上上昇した場合をAKIとするものから、血液透析を要するほどになったものをAKIとして分類するものまで、幅広い考え方が存在していた。AKIの早期診断と重症度分類についての統一的定義が必要であったため、Acute Dialysis Quality InitiativeはRisk-Injury-Failure-Loss-End stage kidney disease(RIFLE)分類を制定した。そして、Acute Kidney Injury Network(AKIN)はRIFLE分類を改変し、さらに進化させたAKIN分類を構築した。RIFLE分類とAKIN分類は、心臓手術後のAKI患者を対象とした前向き研究で用いられ、その妥当性が検証されている。
RIFLE分類とAKIN分類との違いは、微々たるものである。AKIN分類では段階1にsCrが基準時点より0.3mg/dL以上上昇した患者も含め、対象患者の範囲を広げた。これは、たとえわずかでもsCrが上昇すると転帰が悪化するというエビデンスが蓄積されてきたことを踏まえての改変である。一方、RIFLE分類の危険群(AKIN分類の段階1に当たる)は、sCrが基準時点より50%以上上昇した場合となっている。重症患者では特に、尿量の変化がsCrの上昇よりも先行することがあるため、両分類とも尿量についての基準を設けている。AKIN分類では腎機能評価のための観察期間は48時間以内としているが、RIFLE分類では7日間以内である。AKIN分類で48時間以内という制限を設けた理由は、入院患者ではクレアチニンが24-48時間以内のあいだに上昇すると転帰不良であることを示すエビデンスが示されているからである。尿量やsCrに関わらず腎代替療法が行われている患者は、AKIN分類では段階3に相当する。一方、RIFLE分類では腎代替療法の実施期間に応じて、「loss(腎機能喪失)」群または「ESKD(末期腎不全)」群のいずれかに分類される。腎機能喪失群および末期腎不全群に相当するものはAKIN分類にはない。なぜなら、この二つは短期間の腎機能低下の程度を反映する分類ではなく、むしろ何らかの疾患の長期経過の末の転帰または慢性期の状態を反映するものだからである。
RIFLE分類、AKIN分類のいずれにも問題点がある。どちらも腎傷害の部位(尿細管傷害、糸球体傷害など)には言及していない。また、両分類とも血清クレアチニン値を大層重視しているが、この値自体は必ずしもAKIのバイオマーカとして適確ではない。AKI-CPB患者に適用するのにRIFLE分類とAKIN分類のどちらが有用であるかということに関して、はっきりとした一般見解は形成されていない。両分類の概略をtable 1に示した。
教訓 AKI-CPBの発生頻度は平均20-30%です。
2011-07-04 07:34
コメント(0)
外傷患者救急搬送中の輸液で死亡率が上昇する~考察② [critical care]
Prehospital intravenous fluid administration is associated with higher mortality in trauma patients: a National Trauma Data Bank analysis.
Annals of Surgery 2011年2月号より
病院前救護においては「患者をすぐに救急車に乗せて病院へ急ぐ(scoop and run)」方針が妥当であることを裏付けるデータが得られた。このことは、病院到着前に行う手技が増えるほど外傷患者の転帰は悪化することを示唆している。都市では、搬送時間よりも静脈路確保に要する時間の方が長いと考えられ、病院前救護であれこれと手技を行うと、本来ならば救命可能な外傷患者に対して必要な外科的処置を行うタイミングが遅れ、死亡につながる可能性がある。Seamonらの報告によれば、都市に所在するレベル1外傷センターに搬送された外傷患者のうち救急部で緊急開胸が行われた症例では、病院到着前に手技が行われた(stay&play)症例の方が行われなかった(scoop&run)症例よりも生存率が低い。全国外傷データバンク(NTDB)に登録された貫通外傷症例の解析では、病院到着前に脊椎固定を行うと行わなかった場合より死亡率が高いという結果が得られている。ロサンゼルスからの報告では、重症外傷患者は救急隊が搬送した症例より個人の乗用車で搬送された症例の方が生存率が高いとのことである。これと同じ施設から、同じような重症度の外傷患者を救急隊搬送群と一般市民搬送群とに分けて比較する症例対照研究も報告されている。そして、重症度が高い群(ISS 13点以上)では、「一般市民が搬送した方が、救急隊が搬送するよりも外傷センター到着までの時間が短かった(15分 vs 28分);P<0.05」という結果が得られている。このような結果を受け、病院前救護担当者は現場ではなく搬送中に静脈路を確保すべきである、という、搬送時間を延長させずに憶測される輸液の効能を得ようとする妥協案を示す論者も現れるようになった。病院搬送中の静脈路確保の成功率は高く(外傷患者では92%)、状態が不安定な外傷患者では搬送を遅らせてまで現場で輸液を開始すべきではない。
本研究には、遡及的研究であるが故の避けがたい問題点がある。主な問題は、使用したデータベースに記録項目として収載されていない交絡因子があった可能性によって生ずると考えられる。全国外傷データバンク(NTDB)では、搬送時間や、都市と地方の別は記録されていない。したがって、静脈路確保が死亡率上昇につながることと、病院到着までの搬送時間の遅れとのあいだに直接的な因果関係があるのかどうかを検討することはできなかった。また、多重ロジスティック回帰分析において搬送時間についての調整を行うこともできなかったし、都市で発生した症例と地方で発生した症例とを層別化して解析することも叶わなかった。このような解析を行えば、静脈路確保が有効である患者群を同定することができたかもしれない。NTDBの記録では、静脈路が確保されただけの症例と、輸液が行われた症例とを区別することができなかった。また、輸液量(データベースに記録されていない)と死亡率のあいだに容量依存性の関係があるかどうかを解析することもできなかった。以上のような問題点があったため、輸液が死亡率上昇につながる理論的背景を突き止めることはできなかった。輸液によって死亡率が上昇するのは、静脈路確保によって搬送時間が延長するためなのであろうか?それとも、不適切な生理学的目標のもとに輸液製剤を投与することによって出血が余計に増えるせいなのであろうか?静脈路確保の有無についての記録が実際とは異なる場合、その齟齬の仕方は一通りに限られると思われる。つまり、静脈路を確保したのにそれをきちんと記録しない、というものである。そして、静脈路が確保されていないのに、確保したと記録するとは考えがたい。したがって、この記録ミスのせいで、本来は静脈路確保群に分類されなければならない患者が静脈路確保なしの群に分類されてしまい、両群の死亡率の差を縮めることになった可能性がある。NTDBへのデータ提出は各外傷センターの自主性に任されており、全項目にわたってデータを報告することが求められているわけではない。そのため、病院前救護において行われた手技の有無についてのデータが報告されていない症例が多数にのぼった。我々は、データ一部欠落症例は100%ランダムに発生し、病院到着前の輸液によって死亡率が上昇するという観測結果を揺るがすような影響はなかったと考えている。
大規模データベースであるNTDBを用いたという本研究の絶対的な強みは、以上のような潜在的問題点を打ち消していると言えよう。NTDBは、これまでに構築されてきた外傷症例登録システムのなかで最多のデータ登録数を誇っている。だからこそ本研究では、全国から集められた膨大な数の外傷症例データを解析することができた。NTDBは逐次改良されているため、いずれはもっと詳細な病院前救護データ(搬送時間、搬送手段、治療内容など)を解析することができるようになるであろう。今回使用したデータよりさらに信頼性の高い堅固なデータが記録されたNTDBコホートを対象とした同様の研究が、将来再び行われるであろう。そうすれば、前述の問題点の解決につながると考えられる。
病院到着前の輸液が有効であることを示すエビデンスは存在しないのに、外傷患者に対する病院前救護の領域では輸液が標準的治療であると捉えられてきた。外傷症例における病院到着前の各種手技の有効性については未だに賛否両論がある。最近の新しいエビデンスは、この問題に確固とした答えを提示すると言うより、むしろその有効性に疑義を呈するものが多い。「患者をすぐに救急車に乗せて病院へ急ぐ(scoop and run)」方針の支持者は、病院到着前にいろいろ手技をやろうとせず、病院への迅速な搬送を最優先すべきであると主張している。一方、「現場でいろいろやる(stay and play)」方針の支持者は、適切に選択した手技を実施すれば病院到着時に生存している患者が増え、脳損傷後の神経学的転帰が改善する可能性があると考えている。臨床上の重大な問題の中には(この考察で取り上げた問題のように)無作為化臨床試験にはなじまないものがある。そういった問題に関しては、観測研究などの手法で答えを見つけるしかないことが多い。錯綜した知見を示す文献が蓄積されているこの分野において、本研究は重要なエビデンスを付け加えることになったと我々は確信している。
まとめ
外傷患者では病院到着前に静脈路を確保すると明らかに有害であることが示された。外傷症例におけるいずれのサブグループにおいても、病院到着前の静脈路確保and/or静脈内輸液は生存率向上につながらない。静脈路確保and/or静脈内輸液による死亡率上昇は、貫通外傷、低血圧、重症頭部外傷および緊急手術症例でとりわけ顕著であった。外傷症例全例においてルーチーンで静脈路を確保し輸液を行う方針は、取りやめるべきである。
参考記事
輸液動態学
正しい周術期輸液
急性肺傷害の輸液管理 少なめvs多め
敗血症性ショック:輸液量が多いほど死亡率が高い
重症感染小児は輸液負荷で死亡率が上昇する
教訓 L.A. からの報告:重症外傷患者は救急隊が搬送した症例より個人の乗用車で搬送された症例の方が生存率が高い。重症度が高い群(ISS 13点以上)では、「一般市民が搬送した方が、救急隊が搬送するよりも外傷センター到着までの時間が短かった(15分 vs 28分);P<0.05」。(Paramedic vs private transportation of trauma patients: effect on outcome. Arch Surg. 1996;131(2):133–138. Emergency medical services (EMS) vs non-EMS transport of critically injured patients: a prospective evaluation. Arch Surg. 2000;135(3):315–319.)
カナダからの報告:病院前救護体制全体として必要であれば必ず二次救命処置を完全に行うプログラムを導入しても、外傷患者全体の転帰は改善せず、重症頭部外傷患者においてはむしろ転帰が有意に悪化する。(The OPALS major trauma study: impact of advanced life-support on survival and morbidity.CMAJ. 2008;178(9):1141–1152.)
→stay&playの負け、scoop&runの勝ち。
Annals of Surgery 2011年2月号より
病院前救護においては「患者をすぐに救急車に乗せて病院へ急ぐ(scoop and run)」方針が妥当であることを裏付けるデータが得られた。このことは、病院到着前に行う手技が増えるほど外傷患者の転帰は悪化することを示唆している。都市では、搬送時間よりも静脈路確保に要する時間の方が長いと考えられ、病院前救護であれこれと手技を行うと、本来ならば救命可能な外傷患者に対して必要な外科的処置を行うタイミングが遅れ、死亡につながる可能性がある。Seamonらの報告によれば、都市に所在するレベル1外傷センターに搬送された外傷患者のうち救急部で緊急開胸が行われた症例では、病院到着前に手技が行われた(stay&play)症例の方が行われなかった(scoop&run)症例よりも生存率が低い。全国外傷データバンク(NTDB)に登録された貫通外傷症例の解析では、病院到着前に脊椎固定を行うと行わなかった場合より死亡率が高いという結果が得られている。ロサンゼルスからの報告では、重症外傷患者は救急隊が搬送した症例より個人の乗用車で搬送された症例の方が生存率が高いとのことである。これと同じ施設から、同じような重症度の外傷患者を救急隊搬送群と一般市民搬送群とに分けて比較する症例対照研究も報告されている。そして、重症度が高い群(ISS 13点以上)では、「一般市民が搬送した方が、救急隊が搬送するよりも外傷センター到着までの時間が短かった(15分 vs 28分);P<0.05」という結果が得られている。このような結果を受け、病院前救護担当者は現場ではなく搬送中に静脈路を確保すべきである、という、搬送時間を延長させずに憶測される輸液の効能を得ようとする妥協案を示す論者も現れるようになった。病院搬送中の静脈路確保の成功率は高く(外傷患者では92%)、状態が不安定な外傷患者では搬送を遅らせてまで現場で輸液を開始すべきではない。
本研究には、遡及的研究であるが故の避けがたい問題点がある。主な問題は、使用したデータベースに記録項目として収載されていない交絡因子があった可能性によって生ずると考えられる。全国外傷データバンク(NTDB)では、搬送時間や、都市と地方の別は記録されていない。したがって、静脈路確保が死亡率上昇につながることと、病院到着までの搬送時間の遅れとのあいだに直接的な因果関係があるのかどうかを検討することはできなかった。また、多重ロジスティック回帰分析において搬送時間についての調整を行うこともできなかったし、都市で発生した症例と地方で発生した症例とを層別化して解析することも叶わなかった。このような解析を行えば、静脈路確保が有効である患者群を同定することができたかもしれない。NTDBの記録では、静脈路が確保されただけの症例と、輸液が行われた症例とを区別することができなかった。また、輸液量(データベースに記録されていない)と死亡率のあいだに容量依存性の関係があるかどうかを解析することもできなかった。以上のような問題点があったため、輸液が死亡率上昇につながる理論的背景を突き止めることはできなかった。輸液によって死亡率が上昇するのは、静脈路確保によって搬送時間が延長するためなのであろうか?それとも、不適切な生理学的目標のもとに輸液製剤を投与することによって出血が余計に増えるせいなのであろうか?静脈路確保の有無についての記録が実際とは異なる場合、その齟齬の仕方は一通りに限られると思われる。つまり、静脈路を確保したのにそれをきちんと記録しない、というものである。そして、静脈路が確保されていないのに、確保したと記録するとは考えがたい。したがって、この記録ミスのせいで、本来は静脈路確保群に分類されなければならない患者が静脈路確保なしの群に分類されてしまい、両群の死亡率の差を縮めることになった可能性がある。NTDBへのデータ提出は各外傷センターの自主性に任されており、全項目にわたってデータを報告することが求められているわけではない。そのため、病院前救護において行われた手技の有無についてのデータが報告されていない症例が多数にのぼった。我々は、データ一部欠落症例は100%ランダムに発生し、病院到着前の輸液によって死亡率が上昇するという観測結果を揺るがすような影響はなかったと考えている。
大規模データベースであるNTDBを用いたという本研究の絶対的な強みは、以上のような潜在的問題点を打ち消していると言えよう。NTDBは、これまでに構築されてきた外傷症例登録システムのなかで最多のデータ登録数を誇っている。だからこそ本研究では、全国から集められた膨大な数の外傷症例データを解析することができた。NTDBは逐次改良されているため、いずれはもっと詳細な病院前救護データ(搬送時間、搬送手段、治療内容など)を解析することができるようになるであろう。今回使用したデータよりさらに信頼性の高い堅固なデータが記録されたNTDBコホートを対象とした同様の研究が、将来再び行われるであろう。そうすれば、前述の問題点の解決につながると考えられる。
病院到着前の輸液が有効であることを示すエビデンスは存在しないのに、外傷患者に対する病院前救護の領域では輸液が標準的治療であると捉えられてきた。外傷症例における病院到着前の各種手技の有効性については未だに賛否両論がある。最近の新しいエビデンスは、この問題に確固とした答えを提示すると言うより、むしろその有効性に疑義を呈するものが多い。「患者をすぐに救急車に乗せて病院へ急ぐ(scoop and run)」方針の支持者は、病院到着前にいろいろ手技をやろうとせず、病院への迅速な搬送を最優先すべきであると主張している。一方、「現場でいろいろやる(stay and play)」方針の支持者は、適切に選択した手技を実施すれば病院到着時に生存している患者が増え、脳損傷後の神経学的転帰が改善する可能性があると考えている。臨床上の重大な問題の中には(この考察で取り上げた問題のように)無作為化臨床試験にはなじまないものがある。そういった問題に関しては、観測研究などの手法で答えを見つけるしかないことが多い。錯綜した知見を示す文献が蓄積されているこの分野において、本研究は重要なエビデンスを付け加えることになったと我々は確信している。
まとめ
外傷患者では病院到着前に静脈路を確保すると明らかに有害であることが示された。外傷症例におけるいずれのサブグループにおいても、病院到着前の静脈路確保and/or静脈内輸液は生存率向上につながらない。静脈路確保and/or静脈内輸液による死亡率上昇は、貫通外傷、低血圧、重症頭部外傷および緊急手術症例でとりわけ顕著であった。外傷症例全例においてルーチーンで静脈路を確保し輸液を行う方針は、取りやめるべきである。
参考記事
輸液動態学
正しい周術期輸液
急性肺傷害の輸液管理 少なめvs多め
敗血症性ショック:輸液量が多いほど死亡率が高い
重症感染小児は輸液負荷で死亡率が上昇する
教訓 L.A. からの報告:重症外傷患者は救急隊が搬送した症例より個人の乗用車で搬送された症例の方が生存率が高い。重症度が高い群(ISS 13点以上)では、「一般市民が搬送した方が、救急隊が搬送するよりも外傷センター到着までの時間が短かった(15分 vs 28分);P<0.05」。(Paramedic vs private transportation of trauma patients: effect on outcome. Arch Surg. 1996;131(2):133–138. Emergency medical services (EMS) vs non-EMS transport of critically injured patients: a prospective evaluation. Arch Surg. 2000;135(3):315–319.)
カナダからの報告:病院前救護体制全体として必要であれば必ず二次救命処置を完全に行うプログラムを導入しても、外傷患者全体の転帰は改善せず、重症頭部外傷患者においてはむしろ転帰が有意に悪化する。(The OPALS major trauma study: impact of advanced life-support on survival and morbidity.CMAJ. 2008;178(9):1141–1152.)
→stay&playの負け、scoop&runの勝ち。
2011-07-01 07:31
コメント(0)



